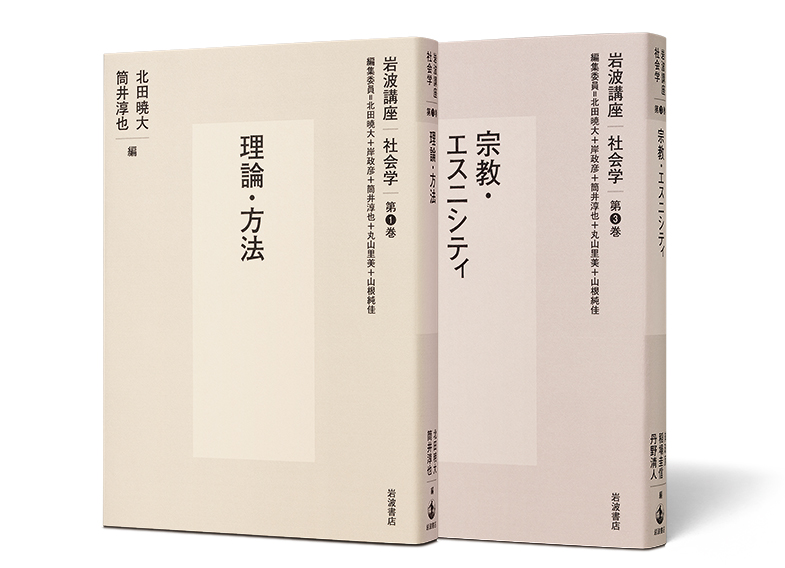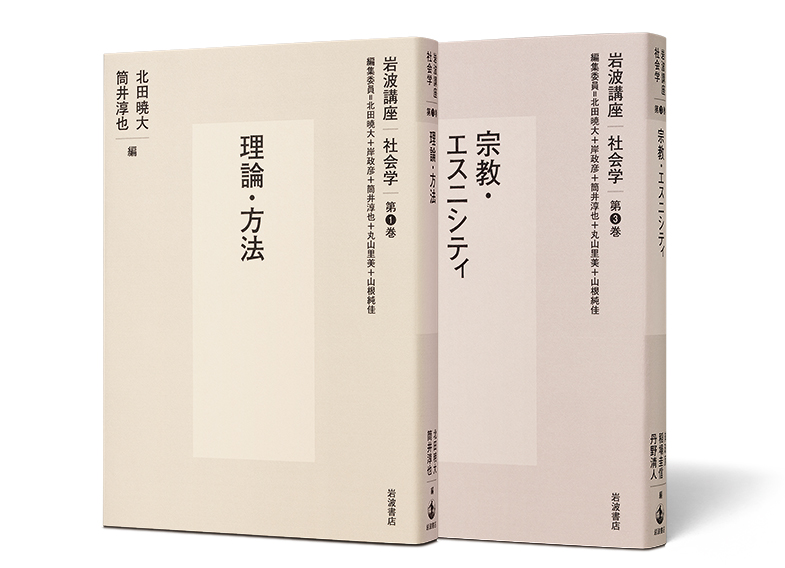
このページには、2023年10月から刊行がスタートした『岩波講座 社会学』第一巻「理論・方法」に収録が予定されていたものの不掲載処置を受けた論考の一部を掲載しています。 このページに掲載したのは、今回新たに執筆し先頭に置いた「再録にあたっての覚書」(のみ)です。
依頼内容は、2007年に刊行した小宮友根さんとの共著論文「社会システムの経験的記述とはいかなることか*」の再録でした。不掲載の主要な理由は原稿の提出が大幅に遅れたため であり、この点については大変申し訳なくおもっています。が、同様の事情にあった執筆者たちが他にも複数名いたところ、不掲載扱いとされたのは私たちだけでしたので、その判断・処置に至った経緯の不明瞭さについては疑問も感じています(なにしろ私たちは、編集部から「いつまでに提出しなければ受け取れない」といった事前通告を受けていないのでした)。
- 北田暁大+岸政彦+筒井淳也+丸山里美+山根純佳編 岩波書店、2023年-
* 酒井泰斗+小宮友根「社会システムの経験的記述とはいかなることか一意味秩序としての相互行為を例に」(ソシオロゴス 31、2007年)。 なお、この論考はその後、小宮友根(新曜社、2011年) に再録されています:

0 再録にあたっての覚え書き(酒井泰斗)
本章の原論文は2007年3月に公刊され、のちにに若干の改稿のうえ再録されている。今回の再録にあたり、分量の制限から第四節全体ならびに多数の注を削除した。
原論文執筆当時、我々は、エスノメソドロジーの論文集と概説書の制作渦中にあり、原論文も、その作業の一貫として、出版において果たすべき課題の自己確認のために執筆したものであった。原論文が作業の出発点における課題の明確化を行おうとしたものであったのに対し、二冊目の論文集では、完了した作業を振り返るかたちで同じ課題に取り組んでいる。したがって両者をセットで読んでいただくと双方の理解に資するはずである。
「あとがき」の方に記したように、この間に筆者の一人(酒井)が中心的に取り組んでいたのは、社会学研究における思考・作業・議論などの抽象水準の制御という課題だった。具体的な資料・データをベースに進められる経験的な学としての社会学の研究実践においては、様々なポイントで、個別の資料よりも抽象度の高い反省的考察が必要となる。これまでの社会学の伝統は、それを「理論」というタイトルで(そして具体的なものと抽象的なものとの関係は〈実証/理論〉という区別のもとで)扱ってきたが、〈具体/抽象〉区別を扱うやりかたには他のオプションもありえ、エスノメソドロジーはその具体例を与えている。 ──「あとがき」に書いたのはそういうことだが、原論文の方は ルーマン理論のエスノメソドロジー的な検討を介して 〈経験的なもの/理論的なもの〉の区別の再考を促したものであり、「あとがき」にたどり着くための道筋を与えたものである。
原論文に対する反響は主要には二つあり、どちらも筆者(酒井)にとっては驚くべきものだった。一つは経験的研究を推奨するものだと解するものであり、もう一つはルーマン理論に対するエスノメソドロジー研究の優位性を述べていると解するものである(筆者(酒井)はその後社会学の雑誌に投稿することをやめた)。こうした誤認はどちらも、特定の対象に対する記述の具体性 と その記述を社会学的記述にするものの抽象性との関係に対する理解の混乱に基づいているだろう。これはつまり、〈経験的/理論的〉区別の再考を促した我々の論考が あっさりと簡単に〈経験的/理論的〉区別のもとで処理されてしまった、ということを意味するのだろうと思う。
ルーマン理論が個別の論点・局面において述べていることについては、それが現に生じている意味の秩序の記述であるかぎり、エスノメソドロジー的再記述を遂行できる。そうした作業を介してエスノメソドロジー研究は、ルーマン理論の抽象性をエスノメソドロジー研究のしかるべき適切な位置において活用することができるようになる*。両者はたしかに主要な目標を異にしているが、そうであるからこそ、また或る研究の良否は方針・立場・方法などだけによっては決まらないからこそ、経験的研究と学説研究を同じやり方で遂行させてくれる程度に抽象水準が制御された 社会学の財産管理手法が重要になるのである。それは、個々の具体的な社会的実践の痕跡を資料として扱う只中においてこそ 必要となる。しかしルーマン自身は、そうしたやり方ではなく、先行研究を類型論にまとめるという低い抽象水準を進んでおり、我々はそのやり方の抽象性の低さこそを批判したのである。
我々は日々の暮らしのなかで、組織、会議、会話、面談、診察といった言葉を用いて現象の特定・指示をおこなっている。それらの現象をルーマンの方針を採用して記述するというのは、そこにどのような構造/作動のペアがあるのかということを特定しようと試みることに他ならない。ところが、恣意的な基準で設定された類型論を出発点においてしまうと、かえってもともとの現象の、システムとしての輪郭が見えなくなってしまう。それに対して、実際に生じている会話の詳細に目を向けるなら、そこに複数の社会システムが同時に成立していることが見えてくる。「社会システム」という抽象的な対象は、個々の作動という具体的な対象の観察を通してそれを可能にしている構造を描くという仕方によって、初めてその明確な輪郭が記述されうるのである。我々が示したのは、「〈システムがある〉から始めよ」というルーマンの言葉は、そのようにして実際に生じている具体的なものの抽象性を捉えるための方針として受け取ることができるということだった。
* 他方、ルーマン理論によるエスノメソドロジー研究の再記述は幾つかのポイントで必ず挫折するだろうから、逆は簡単には成り立たない。その意味では確かに、筆者(酒井)はエスノメソドロジー研究の方針のほうがルーマン理論よりも はるかに優れていると考えてはいる。
文献
- 前田泰樹ほか編、 2007、 新曜社
- 酒井泰斗ほか編、2009、 ナカニシヤ出版
- 小宮友根、2011、 新曜社
- 酒井泰斗ほか編、2016、 ナカニシヤ出版