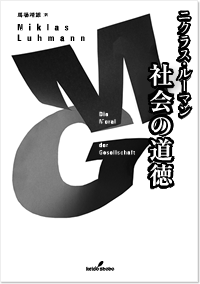
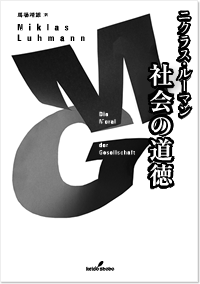 |
|
| 邦訳目次 | 原著論文タイトルと初出 |
|---|---|
| 第1章 分業と道徳――デュルケムの理論 | 1. Arbeitsteilung und Moral: Durkheims Theorie, in: Emile Durkheim, Über soziale Arbeitsteilung, Frankfurt 1992, S. 19-38. |
| 第2章 社会学的パースペクティブから見た規範 | 2. Normen in soziologischer Perspektive, in: Soziale Welt, 20. Jg. (1969), S.28-48. |
| 第3章 道徳の社会学 | 3. Soziologie der Moral, in: Niklas Luhrnann/Srephan H. pfürrner (Hg.), Theorietechnik und Moral, Frankfurt 1978, S. 8-116. |
| 第4章 政治家の誠実さと、政治の高度な非道徳性 | 4. Die Ehrlichkeit der Politiker und die höhere Amoralität der Politik, in: Peter Kemper (Hg.), Opfer der Macht: Müssen Politiker ehrlich sein?, Frankfurt 1993, S. 27-41. |
| 第5章 政治、民主制、道徳 | 5. Politik, Demokratie, Moral, in: Konferenz der deutschen Akademien der Wissenschafren (Hg.), Normen, Ethik und Gesellschaft, Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1997, S. 17-39. |
| 第6章 経済倫理――それは倫理なのか | 6. Wirtschaftsethik - als Ethik?, in: Josef Wieland (Hg.), Wirtschaftsethik und Theorie der Gesellschaft, Frankfun 1993, S. 134-147. |
| 第7章 相互行為、組織、全体社会――システム理論の応用 | 7. Interakrion, Organisation, Gesellschaft, in: Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung, Band 2, Opladen 1975, S. 9-20. |
| 第8章 われわれの社会においてなおも、放棄されえない規範は存在するか | 8. Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg 1993, S. 1-23. |
| 第9章 パラダイム・ロスト――道徳の倫理的反省について | 9. Paradigm Lost. Über die ethische Reflexion der Moral, Frankfun 1990, S. 9-48. |
| 〔『社会構造とゼマンティク3』 |
10. Ethik als Reflexionsrheorie der Moral, in: Niklas Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik, Band 3, Frankfurt 1989, S. 358-447. |
| 第10章 リスクと危険についての了解 | 11. Verständigung über Risiken und Gefahren - Hilft Moral bei der Konsensfindung?, in: Das Problem der Verständigung: ökologische Kommunikarion und Risikodiskurs, Rüschlikon, 1991, S. 93-110; auch in Politische Meinung 36 (1991), Heft 258, S. 86-95. |
| 第11章 リスクの道徳と道徳のリスク | 12. Die Moral des Risikos und das Risiko der Moral, in: Gorrhard Bechmann (Hg.), Risiko und Gesellschaft: Grundlagen und Ergebnisse inrerdisziplinärer Risikoforschung, Wesrdeurscher Verlag, Opladen 1993, S. 327-338. |
| 編者あとがき
注 |
本書『社会の道徳』は、Niklas Luhmann (hrsg. von Detlf Horster), Die Moral der Gesellschaft, Suhrkamp, 2008 の翻訳である。ただし既訳の存在する第十章は省略した(高橋徹/他訳『社会構造とゼマンティク3』法政大学出版局、第五章「道徳の反省理論としての倫理学」)。
『社会の……』(... der Gesellschaft )は、晩年のルーマンが取り組んでいた、機能分化した各システム(経済、法、芸術など)を記述・分析する一連のモノグラフ・シリーズに共通して付された書名フォーマットである。このシリーズは、ルーマンの死後も遺稿を整理編集するかたちで刊行され続けており、そのいくつかはすでに訳出されてもいる(小松丈晃訳『社会の政治』法政大学出版局など)。本書のタイトルもそれを踏襲しているわけだが、ただしこちらはルーマンによる書き下ろし草稿に基づくものではなく、編者のデトルフ・ホルスター(1942年生、1981年から2007年までハノーファー大学社会哲学教授)が、道徳をテーマとするルーマンの既出論考を集めて配列した一冊となっている。編集の経緯と方針は「編集注記」で述べられているので、そちらをご覧いただくとして、ここでは (1) 訳出に際して留意した点、(2) 訳者から見た編者の姿勢の問題点、(3) 特に注意が必要な論点 について、簡単に述べておくことにする。
訳出にあたってまず思い悩んだのが、道徳を論ずる際に広く用いられる、したがって本書でも頻出する gut/ schlecht をどう訳すかであった。通常ならば「善い/悪い」で「よい」のだろうし、本書でもそれで問題がないようにも思われる。しかし次の二点を考慮して、本書ではこのペアには「良い/劣る」を当てることにした。
第一に、数としては少ないが登場してくる gut/ böse (95頁など、また索引の「悪/悪い Böses/ böse 」の項目を参照)との訳し分け。宗教的な意味合いを含んだ、あるいはより戦闘的な(böse なものを撲滅せよ云々)こちらに「善い/悪い」を当てるのが自然ではないか。
第二に、本書では道徳は、人格の尊敬/軽蔑をめぐるコミュニケーションとして扱われている。善人を尊敬する、というのはよいとしても、悪人を軽蔑すると述べるのは、訳者には違和感がある。悪は憎む、戦う対象ではないか。軽蔑されるのは、人格的に「劣る」人であろう。
またルーマンによれば道徳は、機能的に分化した独自のシステムを形成することはないが、各機能システムにおいて引き合いに出されもする。ルーマンが本書以外でもよく挙げる例だが、スポーツにおけるドーピング、政治における汚職などは、それぞれの機能システムの内部において、道徳の名の下に非難される。これらに手を染めた人を schlecht であると呼ぶ場合、やはり「悪い」というよりも、スポーツ選手としての、政治家としての資格が欠けているという意味で「劣っている」との意味合いが強いように思われる。逆に gut なアスリートないし政治家という賞賛の辞の中には、「尊敬できる」と同時に、当該分野において優れたパフォーマンスを達成しているという要素も含まれており、その点では、「善い」よりもニュートラルな「良い」のほうが適切であろう。
編者のデトルフ・ホルスターは本書のセールスポイントの一つを、ルーマン自身もほとんど忘却していた第二論文(第二章)「社会学的パースペクティブから見た規範」を「発掘」し再刊行したことにあると見なしているようだ。編者あとがきでもこの論文の意義が強調され、この論文を踏まえて道徳と規範が、社会学理論の中心的概念として位置づけられている。しかし訳者から見るとこの理解には、少なからぬ問題が含まれている。
第一に第二章の内容は、70年代初期のルーマン理論の主要論点の一つであり、『法社会学』で詳細に論じられた、規範的予期と認知的予期の区別(本邦ではルーマンの「予期理論」などと呼ばれることもあったが、ルーマン自身はこの呼称は使用していないようだ)の要約にすぎず、しかも両者の再帰的多重化(科学においては認知的予期が支配しているということを科学者は規範的に予期している、と社会学の授業でマートンをめぐって学習し予期する、など)という複雑な事態にはほとんど触れられていない。確かに見通しのよい論考ではあるが、ルーマン理論の形成過程において、編者が考えるほど画期的な意義を持つものとは言えない。
第二に今述べた解釈のゆえに編者は、第三章以降で論じられている、道徳の再帰化の成立史と、再帰化の実践的意義(というよりも、実践において再帰化から生じてくる困難)とをあまり重視しない姿勢を取っている。むしろ編者は、ダブル・コンティンジェンシーという問題の解決策として、つまり社会秩序の不可欠の条件として、道徳を位置づけようとしている。だがダブル・コンティンジェンシーはあらゆる偶然を手がかりとして、言わば自動的に解決されてしまうのであって、特に道徳(だけ)がその解決=秩序形成のために特権的な地位を占めているわけではない。むしろ編者の立場は、秩序維持のためには現行の規範や制度が不可欠だと主張することになり、かつての「ルーマンは現状維持を最優先する保守主義者、ないしはテクノクラートのイデオローグである」との定型的な批判を再燃させてしまう恐れがある。
ルーマンが本書三章以下で強調しているのは、この種の規範の導入による秩序問題の「解決」が、歴史的/社会的に信憑性ある理念素材(ゼマンティク)依拠しての脱パラドックス化=パラドックスの一時的隠蔽にすぎないという点である。それが特に明らかになるのが、良い/劣るのコードを前提にした道徳の設定自体が、はたして良い行いなのか否か……という 再帰的な問いにおいてである。そして、機能分化し固定的な順拠点(中心ないし頂点、あるいは「根拠」)を持たなくなった近代社会では、もはやこの問いに対する疑念の余地のない答などありえないのである。
本書の意義はむしろ、先の「道徳を問うことは道徳的か」という問いへのあらゆる答が一面的であり疑念を孕んでいるということを、第四章以下で経済的公正、政治家の姿勢、テロ、環境問題といったある程度具体的な(ルーマンにしては、だが)問題に即して論じている点に求められよう。その意味で本書は、ルーマンなりの「政治小論集 kleine politische Schriften」としての性格を併せ持っているのである。ルーマンの議論は抽象的な空論だというイメージを抱いておられる読者には、そちらを先に読んでいくほうがいいかもしれない。
ただし各問題に対する「結論」は、例によって例のごとくのルーマン流である。多数の犠牲者が予想されるテロを未然に防ぐために容疑者を拷問してよいかという、きわめてアクチュアルな問い(本稿の骨格は、「イスラム国」による日本人拘束・殺害事件が報じられていた2015年1月末に作成された)に対しても、答は次のようになる。イエス/ノーのどちらの答えも、件の問い、あるいはそれと関連する「合法/違法」(この場合はむしろ、法 Recht=権利と読み替えて「人権の遵守/侵害」か)の問いを、何らかの「不可侵のレベル」(ホフスタッター)の想定によって脱パラドックス化したものに他ならず、それぞれが異なる帰結と派生問題を伴う。したがって一般的な、何らかの原理(理性であれ、討議であれ)によって根拠づけられた答は存在しない。だからとりあえずは、議論において用いられている素材と、当該の結論から生じる派生問題を観察し記述しなければならない。そしてまた、パラドックスの浮上とその隠蔽という事態は社会的にも歴史的にも、決してユニークなものではないという点をも考慮すべきである。全体社会の各機能システムにおいて、コードの折り返しから生じる同様のパラドックスは常に生じているし、継続的に隠蔽され続ける。そして同じ問題が、古代から中世の神学的文脈においても、常に登場してきていた--例えば、地獄は、すなわち善人は天国へ、悪人は地獄へという善/悪の区別は、単なる演出として設定されたものにすぎない。さもなければ(本当に悪人が地獄に落とされるとしたら)、聖母の慈悲は悪魔に敗北したということに──「悪しき」結論に──なってしまうだろうから云々というかたちで(269頁)。ここにおいて課題として登場してくるのは、何らかの答を絶対視し実行することでも、あらゆる答を「脱構築」し宙づりにすることでもない。当該の答を他の社会的・歴史的文脈において提起された答(隠蔽策)と比較することなのである。これこそが『社会の……』シリーズ全体において試みられていたことに他ならない。
この「結論」は、件の問いに対するどんな答も誤っている、「悪い」答であるということを意味するものではない。しかしそれぞれの答がおのおの特有のリスクを孕んでいるとは、言いうるし言わねばならないのである。テロリストへの拷問を、一定の条件の下で認めるようなさまざまな措置が考えられうるだろうが、おそらくはそのどれも、十分に満足すべき解決策というわけにはいかないはずである。しかし、何もせずに無辜の人々をテロリストのファナティズムの犠牲にすることも、もちろん容認できるものではない。
この立場を、フーコーの言葉を借用変形して次のように要約するのは、ルーマンの道徳論の性格づけとして適切だろうと思われる。
私(ルーマン)が言いたいのは、すべての答が悪い(誤っている)ということではなく、すべてがリスキーである(当該選択から損害が生じうる)ということだ。リスキーであるなら私たちには常に、なおも為しうることが残されているはずである。念のために確認しておくならば、これは単なる決断主義ではありえない。選ばれた決定を支える歴史的・状況的文脈および決定から派生する副次的効果を、他の決定のそれと比較することが常に求められているからである。これが、「常に残されている、為しうること」なのである。
本書の中心をなす第三論文「道徳の社会学」では、冒頭から「超理論 Supertheorie」という聞き慣れない概念が登場し、かなりの長さにわたってそれについての議論が展開されている。道徳についての論文中になぜこのような議論を挿入しなければならなかったのか、いったいそれは道徳とどう関係するのかと、疑念を覚えた読者も多いのではないだろうか。
実はこの概念自体、ルーマンの他の諸著作においても縦横に活用されているとは言いがたいところがある。科学システムのコミュニケーションにおける「理論」というものの位置づけに関連するこの概念は、集中的に扱われて当然と思われる『社会の科学』では、索引で一カ所に登場するにすぎない。ルーマンの主要著作と見なされる『社会システム』では序文でのみ扱われており、彼の理論の総決算としての性格を持つ『社会の社会』では索引に載せられてすらいないのである。しかし先に述べた本書の中心的テーマの一つである道徳の再帰化の問題、すなわち「良い/劣るを問うことははたして良いことなのか否か」という設問と関連させて考えれば、なぜこの箇所で超理論について論じられているのかが理解できるはずである。
科学システムにおいては、機能分化した他のシステムとまったく同様に、コードとプログラムの分離が作動の前提となる。コードは、当該システムにおけるあらゆるコミュニケーションの前提となる二分図式であり、科学の場合なら真/非真がそれに相当する。そして個々のコミュニケーションをこの二つの値のどちらかに割り振るのが、プログラムの、科学の場合なら理論の、役割なのである。デユルケムのアノミー論を踏まえて、好況時に自殺が減少するというのは真ではないとされる(少なくとも、アノミー的自殺に関しては)、というようにである。理論は変化交代しうるし、その結果個々の言明が真から非真へと、あるいはその逆方向に、変化しうるとしても、コードは定常に保たれる。あるいはコードの不変性の下で理論の交代が生じることが、科学の動態を可能にするのである。
ところが理論がコードそのものを問題にする可能性も排除されるわけではない。伝統的に「真理論」と呼ばれる議論がその一例であり、マルクスの経済学批判やフロイトの精神分析もまた、真理を特定の利害関心や欲望の顕現として捉えようとしている点で、同様である。そしてルーマンが真理を科学システム特有のコミュニケーション・メディアとして扱い、社会的・歴史的文脈を踏まえて経験的分析の対象とするのも、また同様なのである。このように、理論が自身の前提であるはずの真/非真のコードをも、自身の対象の一部として扱おうとする場合、その理論は「超理論」と呼ばれるのである。
超理論は、単に適応範囲の広い、「社会で生じるありとあらゆるコミュニケーションを普遍的に説明する」(林香里「ルーマン理論とマスメディア研究の視点」、ルーマン『マスメディアのリアリティ』木鐸社、200頁)だけの理論ではない。超理論は、明らかなパラドックスに巻き込まれてしまうのであり、その点にこそ超理論のメルクマールが存している。真と非真について論じる超理論は、はたして真なのか非真なのか、というようにである。これに対しても思想史の中で、さまざまな解決(隠蔽)の試みがなされてきた。真理(真と非真の区別が真であること)はそもそも人間が主体的に把握しうるものではなく、ただ歴史の中で存在の側から開示されるのを待ち受けるしかないというハイデッガー流の受動主義も、その一つであろう。ルーマン自身はこの種の「深遠な」議論を回避して、超理論が対抗的な試みを退けつつ自己の適切さ(「真理性」ではないにしても)を証するために駆使しうるいくつかの戦略を、「全体化」というタイトルの下で指し示している。
この超理論のパラドックスが、先に述べた道徳的な問いのパラドックスと並行するものであるのは、見やすい道理だろう。「良い/劣るの問いは良いか劣るか」--この設問にどう答えても、パラドックスに行き着いてしまう。「劣る」と答えるなら、どんな良いものを指し示しても「良いは劣る」ということになる。逆に「良い」と答えるのなら、では良いものである「良い/劣る」から区別される劣るものとは何なのか、そしてこの高次の良い/劣るの区別自体は良いのか劣るのか……と、さらなる問いが続いていく。
この問題に対する通例的な解決策は、道徳の問いと道徳(道徳コード)についての問いとを分離し、後者は道徳コードとは異なるコード、すなわち真/非真の下で追求されるのだと主張することだろう。周知の、メタ倫理学と規範倫理学の分離は、その一例である。しかしこの脱出策も万全ではない。第一に、この分離と、メタ倫理学のみに議論を限定するという禁欲的姿勢自体が、一つの倫理に基づいており、それははたして学として良いのか、劣るのかとの問いを巻き起こしてしまう。そして第二に、この分離の拠り所となっている科学のコードもまた、同様のパラドックスを内包しているのであって、決して盤石の基盤とはなってくれない。この第二の難点をあらかじめ明示しておき、道徳について客観的に論じればそれでよいのだという脱パラドックス化=隠蔽戦略を退けておくために、超理論についての詳細な議論を差し挟む必要があったのである。そして既に述べておいたように、ルーマンが考えているのは道徳の、また超理論のパラドックスの前で立ちすくんだり瞑想に耽るのではなく、社会的・歴史的な比較手続きを含む全体化戦略によって、さらに観察と記述を続けていくことなのである。
[後略]
訳者より
この度は、拙訳『社会の道徳』をお手にとっていただき、ありがとうございます。すでにお気づきのことと思いますが、本書(初版)には多数の誤りが含まれております。訳出に際していささか無理目なスケジュールを立ててしまったことと、数年来の私の体調不全により注意が行き届かなかったことに起因する事態であり、読者の皆様にご迷惑をおかけしてしまいまことに申し訳なく思っております。
機会があれば訂正するつもりではありますが、とりあえず現在までに気づいた箇所を列挙しておきます。参考にして頂ければ幸いです。
今後もチェック作業を続けて、今回拾いきれなかった箇所も追加して行きます。読者諸賢におかれましても、お気づきの点がございましたらご一報頂きますよう、お願い申し上げます。注記なしの箇所は、単なる誤植です。訳語修正は(訳語変更)、訳文修正は(訳文修正)と明記します。
[55-8]は「訳書55頁8行目」、[66-b3]は「同66頁後ろから3行目」を意味します。
| 誤 | 正 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第一章 | ||||
| [8-11]「道徳的な、また」-[8-14]「ありうるのだ云々」(原書S.15)まで | 「〔デュルケムにとって〕事実としての道徳的行動と、事実としての不道徳的行動が存在するわけではない。存在するならそれらはさらに、おそらくは「道徳性Moralität」ないし「道徳的有意性moralische Relevanz」と呼ばれる、一つの総体的概念(Gesamtbegriff)のうちに取りまとめられうるはずである。ところが〔デュルケムにおいては〕存在するのは連帯と道徳のみであり、両者は特別の事情のもとでは実現を妨げられることもありうる〔だけだ〕とされるのである。」 | 訳文修正 | ||
| 第二章 | ||||
| [27-b6] | 「一定の定められた時点」 | → | 「一定の時点」 | |
| 第三章 | ||||
| [61-6] | 「相応にで分化し」 | → | 「相応に分化し」 | |
| [63-4] | 〔 〕内削除 | 訳文修正 | ||
| [63-5」 | 「今や」 | → | 「この場合」 | 訳文修正 |
| [80-b8] | 「別の構想に抗する」 | → | 「別の構想に移行する」 | |
| [101-8] | 「(Achutug)」 | → | 「(Achtung)」 | |
| [110-10] | 「《あたりまえ》のもの」 | → | 「《あたりまえ〔=陳腐〕》なもの」 | 訳文修正 |
| [147-b8] | 「古代の高分化」 | → | 「古代の高文化」 | |
| 第四章 | ||||
| [161-b6] | 「すで片づけられて」 | → | 「すでに片づけられて」 | |
| [166-7] | 「配されてきたきた」 | → | 「配されてきた」 | |
| [169-b9] | 「典的明証を」 | → | 「典的名称を」 | |
| 第五章 | ||||
| [179-4] | 「単によくあること」 | → | 「単に良くあること」 | |
| [186-9] | → | 〔……〕を、前行「反応する。」の後に移動 | ||
| [187-2] | 「事態観察してみれば」 | → | 「事態を観察してみれば」 | |
| [191- 《5》から2,3行目] | 「より高度の非通常性」 | → | 「より高度の非道徳性」 | 訳語修正 |
| [191-b5] | 「自身の基準が」 | → | 「その基準が」 | 訳文修正 |
| [195-b2] | 「代別する」 | → | 「代弁する」 | |
| 第七章 | ||||
| [235-b7] | 「次のような根本過程によって」 | → | 「次のような根本仮定によって」 | |
| 第八章 | ||||
| [243-8] | 「さらないまた都市や」 | → | 「さらにまた都市や」 | |
| [244-10,11] | 「自然的な団体(Körpern)」 | → | 「自然的な団体=身体(Körpern)」 | 訳語修正 |
| [252-b7] | 「価値連合」→ | → | 「価値衝突」 | 訳語修正 |
| [252-b3] | 「連合問題」 | → | 「衝突問題」 | 訳語修正 |
| [253-2] | 「連合事例」 | → | 「衝突事例」 | 訳語修正 |
| [253-4] | 「価値連合」 | → | 「価値衝突」 | 訳語修正 |
| [253-3] | 「規則/例外図式-規則」 | → | 「規則/例外図式という規則」 | 訳文修正 |
| 第九章 | ||||
| [265-8] | 「必要になったという点は」 | → | 「必要になったという事態は」 | 訳文修正 |
| [265-9] | 「〔階層化された、〕」 | → | 「〔階層化された〕」 | |
| [276-7,8] (二カ所) |
「優位性」 | → | 「標準」 | 訳語修正 |
| [278-b5] | 「近代的価値定位」 | → | 「近代的な世界定位」 | 訳語修正 |
| [280-b2] | 「そうできねばならないだというということ」 | → | 「そうできねばならないということ」 | |
| 第十章 | ||||
| [282-6] | 「整えおく」 | → | 「整えておく」 | |
| [283-b9] | 「リアリティは補足」 | → | 「リアリティは把握」 | |
| [286-11] | 「旧来の。福祉国家」 | → | 「旧来の福祉国家」 | |
| 第十一章 | ||||
| [299-b5] | 「生活権」 | → | 「生活圏」 | |
| [301-1] | 「ルーティンによって」 | → | 「ルーティンとして」 | 訳文修正 |
| 編者あとがき | ||||
| [315-b7] | 「《=諸システムがある」 | → | 「《諸システムがある」 | |
| 編者注記 | ||||
| [335-b1] | 「Arbeirsteilung」 | → | 「Arbeitsteilumg」 | |
| 原注(以下、[337-5]は「375頁注5」の意味) | ||||
| [340-20] | 「confingency」 | → | 「contingency」 | |
| [342-11] | 「次の点は明だから」 | → | 「次の点は明白だから」 | |
| [378-7] | 「受けいられる」 | → | 「受け入れられる」 | |
| [389-22] | 「srructure」 | → | 「structure」 | |
| [392-11] | 「CharIes」 | → | 「Charles」 | |
| 原注 | ||||
| [396-6] | 「飛躍的増大する」 | → | 「飛躍的に増大する」 | |
| [398-15] | 「ザドルガニに言及している」 | → | 「ザドルガに言及している」 | |
| [398 第四章3] | 「(1920- )」 | → | 「(1920-2015)」 | |
| [399-5」 | 「という点事態は」 | → | 「という事態は」 | |
| [400-1] | 「ことになるから」 | → | 「ことになるから。」 | |
| [401 第十章1(b4)] | 「まことの患者」 | → | 「まことの愚者」 | |
| [402 1行目] | 「(ルタサール)」 | → | 「(バルタサール)」 | |
| [404-7] | 「できなかった。」 | → | 「。」を、次行「)」の後に移動 | |
本訳書についてお気づきの点があれば  までお報せください。
までお報せください。