出口弘『社会の科学』書評(週間読書人 2010.05.21)の構成
- 1.はじめに
- 2.社会の科学を問う
- 3.継承すべきもの
※PDFファイルへのリンク(準備中)
1:モデルとシステム概念について
前提
- 【T1】 [システムはモデルである]システム科学において、システムは認識のためのモデルである。[出口書評 第2節第3段落]
- 【T2】 [システムはモデルではない]パーソンズにとってシステムは分析モデルであったが、ルーマンにとっては現実存在する対象を指示するための概念である。
出口さんは、ルーマンが「社会システム」を「あたかも実在の対象のように」扱っているというが[書評2節第2段落]、 これはルーマンが建前レベルで掲げている方針に由来するものである(たとえば『社会システム』(1984)第1章冒頭を参照)。 ともかくも、「システム」という語の用法について、【T1】と【T2】は 相容れない主張をしているわけで、これは調停されなければならない。 言い換えるとこれは要するに、ルーマンの語用が通常のシステム科学者のそれから非常識に著しくズレているのでシステム屋さんが迷惑しており、また話そのせいでも通じないので困る、といった問題である。
選択肢
調停の方向は形式的にはいくつか考えられる:
- ■術語使用のレベルで解決する:
- 【P1】 T1 を認めた上で、ルーマニ屋が「システム」という語の使用をやめる。[酒井案]
- 【P2】 「システム」という語を、「モデル」としてではなく対象を指示するものとして使用することに権利があることを示す。[ガチ]
- ■目標を変更する:
- 【P3】 T1 にあわせて、作業目標を通常のシステム論に合わせて(メタ言語の設計・理論構築へと)変更する。[出口案
?]
私自身としては──ルーマン理論から「システム」概念を取り去っても特に困らないと考えるので──【P1】で構わない。
しかし、上述のような迷惑にもかかわらず 今後も断固として「システム」概念に固執し続けたいというルーマニ屋には、
やはり断固として作業【P2】をして──ひとさまにかける迷惑を補って余りある意義があることを示して──いただくのが筋というものだろう。
それはそれとして。
議論
出口さんのほうはといえば、おそらく【P3】を提案しているのだろうと思われる。しかし、この提案に際して、そうしてしまうとルーマンの持っていた作業目標が変質してしまうことが考慮されているのかどうか、それが定かではない。酒井&小宮(2007)*で論じたのは この作業目標についてであり、そこで我々は次のように主張した(口頭で簡単には説明できないから わざわざ論文を書いたわけなので、粗筋以上の内容については ぜひ論文を参照していただきたい):
- 【T2】は 学史に根を持つ問題への解答例であり、社会学方法論としての意義がある。
- ただし、ルーマン自身はその方針を うまく遂行できていない。
- この課題は遂行可能である(なにしろ遂行例がすでにある)。
- ルーマン自身がおこなった様々な仕事は、そうした遂行例も参考にしながら、上記方針に即して再検討されるべきであり、経験的な学としての社会学においてルーマンの遺産を活用する道は その方向で模索されるべきである。
「F1:モデルを作って研究を行うこと」ができるのは、誰でもが知っている。しかし、「F2:モデル作成=理論構築を目指さなくても研究は可能であること」は、それほど知られていない。ルーマンのテクストが混乱しているように読めるのは──実際、混乱していると私は思うのだが──、F2 を指向しているにも関わらず、それを「システム論の(したがって F1の)助けを借りて」行おうとしているからではないかと私は思う。(言い換えると、F1 を F2 で書き換えることがルーマンのおこなった作業の大部分であり、その作業半ばで彼は死んでしまった、ということ。)
出口さんが、後者のやり方(F2)も認めるのかどうかは尋ねてみたい**。出口さん自身は それにはコミットしないだろうが、それはさておき、こうしたスタンスがあることを一旦は認めてからでなければ、ルーマンのテクストの適切は評価は(そして、標準的なシステム論との コンタクト可能性の改めての模索も)できないはずであるから。
** 合評会の場では、「P3 は認める。F2 は理解不能。」という趣旨のお返事をいただいたと思う。
出口さんからのリプライ
【T2】は 学史に根を持つ問題への解答例であり、社会学方法論としての意義がある。私にとっては、これこそ問題、社会科学の方法論が物理的な実在主義を取ったら全ておしまいと思っている。志向対象は超越であり、志向対象に名前をとりあえずつけるのはよいが、範疇的構成物は認識する側の問題。これはフッサールも含めての共通項。
ただしそれではこちらが構成した範疇的構成体の意味論的根拠をどうするかで、英米流の意味論は、社会的な集合表象につながる「範疇的意味」概念を内包として構築できていない。(むろんモンタギュー文法や可能世界意味論はここでいう内包的意味論としては失格)
私自身は、これを不確定指示子という論理学に導入した概念等を使い、形式意味論としても構築している。 (出口弘、小津正直、集合論的不確定指示子による理論間関係の論理分析、科学基礎論研究、Vo1.28 No1.)
「F2:モデル作成=理論構築を目指さなくても研究は可能であること」例えば、構築主義的な研究や、フィールドワークは、対象そのものに向き合っているのではなく(自然科学でないので)、 主体が構築した解釈の世界を対象として、それをこちら側のコンテクストの違う範疇的構成体で再解釈するのではなく、 対象の社会なり集団が構築した意味世界を「理解」する方法であり、或はそうした意味を構築するある種のアクションリサーチである。** 合評会の場では、「P3 は認める。F2 は理解不能。」という趣旨のお返事をいただいたと思う。
超越としての対象に向き合って何かをハンドリングしているのではない。というのが私の言いたい事。
2:ルーマンの議論はどこで止まるか
しかし問題はそこにオートポイエシスという思考停止ワードが入ることだろう。一定の問題関心に基づいた社会的知の構成に対する方法論的批判を包摂した知のありようは、オートポイエシスという実質的にはそこで分析的な思考が停止してしまうようなメタ的な説明の論理を用いることなく構築されなければならない。 [書評3第2段落]
同意する。
とはいえ、問題は ここで何が起きているか ということのほうである。「依拠しているモデルがオートポイエーシス──ひいては、山師フェルスター率いる BLC 系統の諸理論──だからダメだ」という主張は、そのモデルに「欠陥がある」とか「生産性がない」からダメなのだ と言っているように聞こえる(これはこれで正しい主張であるように思われるが)。その場合、解決策は「モデルを別のものへと取り替えること」だということになるだろう。
しかし、残念ながら、問題はそうしたところばかりにあるわけではないように思われる。
ルーマンの この上なくダメな議論の例
ルーマン(1986)「生活世界:現象学者たちとの対話のために」(青山治城 訳)からの引用:
このような状況のなかで出口を見い出すためには、現象の世界をその思考的変様に耐える本質的な相において記述するという[フッサール的な]方法 はやめて、オペレーショナルな接近法を求めなければならない(15)。 オペレーション は すべて ある区別distinction によって始められる。あるオペレーションは、それ自体が一つの区別なのであり、区別なしには始まらない。あらゆるオペレーションは、それが接続しうる区別をいつも事実としてあらかじめ前提している。したがって、それをこの概念の核心とするのではないにしても、「いつもすでに与えられている」ことを強調するような生活世界の定式が好まれることも理解できる。{この定式が示すように}生活世界がいつもすでに与えられていることによって 人は事柄に適した行動をすることができるのであるが、しかしそれによって同時に、生活世界においてのみ・生活世界内の現象についてのみ 有意味な問い──即ち 生活世界の構成 という問題──は排除されてしまう。 こうしたディレンマから抜け出す道はあるのだろうか。生活世界の内部にいながらあたかもその外部にいるかのように──空虚な空間のなかで生活世界がすでに生じているところから出発することができると考えることができるような──、十分に誤った、全く抽象的な理論が存在しうるのであろうか? われわれは十分に誤ったという点を意図的に強調したい。なぜなら、われわれにとって問題なのは、まさに誤った前提から正しい認識が生じるというパラドックスの解消にあるからである。そしてこれこそが、[現象学のように]主観に立ち戻って再確認することを省略する手がかりとなる。
ここで求める理論をわれわれはジョージ・スペンサー・ブラウンの論理学のうちに見ることができる(16)。この論理学は「マークのない空間」から始まる。その後われわれは、一つの境界線を引けという指令をうける。われわれは一つの区別によって空間に印をつける。しかし、それは、区別されたいずれの側がその後のオペレーションにとって出発点となり、どちらが接続点となるかを指示することができる限りにおいてのみ意味をもつ。 それゆえ、区別することは同時に──ある区別に基づいてのみ意味をもち・別の区別の枠内では別の意味をもつような── 一つの指示indication をも同時に要求する。区別 および 指示 は、基本的に同一のオペレーションの二つの契機にすぎない。したがって、スペンサー・ブラウンが彼の算法を構成するために必要とする唯一の演算記号はである。
(15) われわれはここおよび以下で、オペレーション という抽象的な表現を用いるが、それは意識の志向的 オペレーション(フッサールのいう志向性)が問題であるのか、それともある社会システムのコミュニカティーフなオペレーションが問題なのかは未決定にするためである。[ここで用いるオペレーション概念には]両者が含まれるのであるが、現象学の理論構成とは違って社会的現象を意識の作用に還元することはしない。
(16) Laws of Form. 2.Aufl., London 1971. を見よ。われわれは勿論、自己言及的な契機を構成する論理学と代数学の基礎づけを目指すこの理論に従うわけではなく、最初の第一歩を共に遂行した後はそこから離れる。しかし、たとえたまたまそれを利用することができるというだけであるにしても、われわれはこれとの親縁性を重視する。
この引用箇所の場合、準拠問題は、「フッサールの議論を、主観性への依拠なしに=社会システムにも 使えるようにしたい」というものであり、それに対してルーマンが進もうとしているのは、「議論を一旦抽象化したうえで、他のものにも使えるようにする(=一般化)」という方向だといえるだろう。いまその点は認めておくとして、問題は、
- どのように抽象化するか
- どうやって当初の目標(=社会システム=コミュニケーション)へと着陸するか
である。ルーマンの議論は この どちらの点でもおかしい。
[1] 抽象化のやり方がおかしい: スペンサー=ブラウンを参照しているのがおかしく、かつ、利用の仕方がおかしい
ルーマンは、上記引用箇所に引き続く段落で
、なんとスペンサー=ブラウンの謂う「圧縮」と「再認」は、社会過程では成り立たないと述べている。ならばともかくも、ふつう議論は「したがって、それは社会学には使えない」と続いて、そこで話は終わるはずである。しかしルーマンはスペンサー=ブラウンの参照をやめないし、さらに「再参入」概念も──これは「圧縮」と「再認」を前提にして導かれるものなのに!──使用するのである。
ここでルーマンができているのは、せいぜいフッサールの謂う「沈殿」を、「圧縮」という言葉に取り替えた程度のことである。ところが、上述のように、ルーマン自身がそれら(圧縮や再認など)から概念間との結びつきの制約を取り外してしまっているのだから、この言葉は──イメージを喚起する以上の──どんな仕事もすることができない。要するにここでは、なにか作業が進んだわけではなく、「むしろ何も言わなかったほうがよかった」と言えるくらいに後退・混乱しているのである。
というのも、もしも「区別」「操作」「観察」~~などなどからなる術語の体系がいわゆる「メタ言語」なのだとするなら、それは形式的には筋の通ったものでなければならないはずであるが、ここに そんなものはないのである。常識的に考えて、意味を持たず、概念の関係も(ごくごく部分的にしか)決まっていない 無駄に抽象的なターミノロジーでもって、しかも、具体的にどういう経験的なマテリアルに関する言明であるのかも示されないままに繰り広げられる議論を 理解できないことは、おかしなことではまったくない。しかし実際、ルーマンのテクストは、しばしばそういうものなのだ。
そこで、ルーマンを読もうとすると、その努力の半分以上は、こうした(馬鹿馬鹿しくトリヴィアルな理由によって)理解しがたいことになっている文言を解読することにあてられざる得なくなる。それらの文は しばしば、「クイズ」である資格すら持っていない──なぞらえるにふさわしいのは「なぞなぞ」や「頓知」といったものだろう──のに。
同じことは、次のようにも言える。
[2] 抽象化したあとで帰還する方策を持っていない
つまりルーマンは、「社会システムの経験的な作動」へと着地するやり方を 結局は編み出せなかった、ということ。
数学やシステム理論が社会学的議論の抽象化を助けてくれる ということはあるかもしれないが、しかし「何を・何のために」抽象化するべきなのか という問いに対する答えを与えてくれるなどということは(論理的に)ありえない。それは社会学的に与えられるしかないのだから、考察は社会学の範囲で行われなければならない。そして、まさにルーマンに欠けている*のは、そうした営為であるように思われる。
常識的かつ穏当に考えて、「まず抽象化を行って、しかるのちに具体物に適用する」などというやり方を取る必要はなく、具体的な経験的マテリアルの記述・分析を試みるなかで 必要な抽象を継続的に試みる、という作業を積み重ねつつ議論を進めればいいだけだと思うのだが、ルーマンにはそうした作業をおこなう気もないように見える。
ほかの例
こうした例は、ルーマンのテクストから いくらでも拾ってこれる。
論文(注8)で我々が指摘した「予期」の問題もそうである。この概念は、社会システムのもつ規定性(=システム構造)を、もう一歩具体的に表現するために導入されているものだが、具体化の方向が間違っている。たとえば、「予期」は心的なカテゴリーではない とは言われるが、「では積極的に何であるのか」──そしてその概念は、「作動の記述」という課題に対してどのような示唆を与えるのか──に対する答えはない。こうしたあいまいで無規定な概念では、経験的研究とのコンタクトは望めないし、そこを無理に進めば 示唆よりは混乱を与えることになるだろう。
『社会の科学』では「帰属」の問題が目立つ。
真偽に照準したコミュニケーションは、「体験」に焦点があたるかたちで進む という着眼は検討に値するものだろう。
ところが──各機能システム間の比較を行っているうちは、いちおうこれでも議論が進められるが──、科学に関わるやりとりについて、もっと立ち入った検討をしようとすれば、もちろんそれでは済まない。〈体験/行為〉がコミュニケーションにおけるにおける(原因・理由・意図・動機などの)帰属のありようによって構成される、というのがルーマンの主張なのだから、ならば帰属のありようは、個々のやりとりに即して 具体的に捕捉できるのでなければならない。そしてまさに、そうした作業が求められる箇所で・そうした作業をするしかないところで、それが行われる代わりに、やはり「オートポイエーシス」という「言葉」に頼って 陳述は「切り抜け」られていく。
※ご参考
別の言い方をすると、ルーマニ屋に欠けているのは、こうした↓水準での概念化の努力ではないか。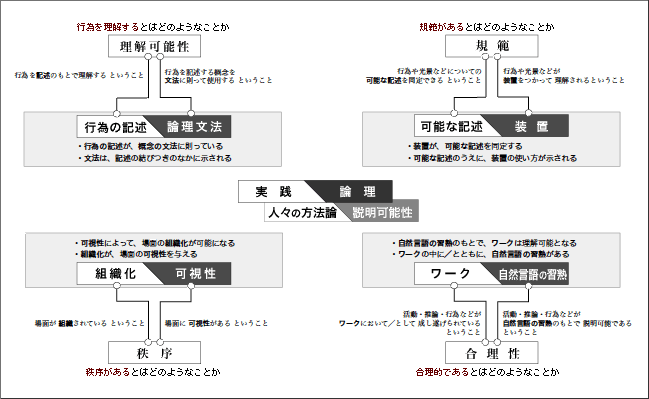
出口さんからのリプライ
区別することは同時に──ある区別に基づいてのみ意味をもち・別の区別の枠内では別の意味をもつような── 一つの指示indication をも同時に要求するこのあたり、ルーマンからサルベージするのに、区別=境界化されたモデル という方向でやっている。
拾遺:循環性、主体、表象
時間が(すごく)あれば。
「循環性」──というよりも*、「すなわち」の関係(=構成関係)──についての研究について。
たとえば「システム構造/システム要素」の構成関係は「同時的」なものである(=順番を持った出来事の配列ではない)が、「循環」という語では この事態を適切には表現できないだろう。