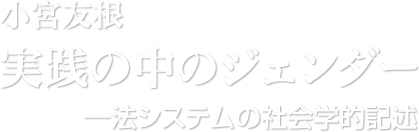| まえがき I 部 社会秩序の記述 第1章 性現象の「社会」性 第1章補論 行為とコンテクストの相互構成的関係 あるいは間接的言語行為について
第2章 社会システムの経験的記述第3章 社会秩序の記述と批判 |
II 部 法的実践の中のジェンダー 第4章 法的推論と常識的知識 第5章 強姦罪における性的自由 第6章 被害者の意思を認定する 第7章 ポルノグラフィと「女性の被害」の経験 |
あとがき 文献 人名索引 事項索引 |
| このページは、小宮友根『実践の中のジェンダー』(新曜社・2011年9月刊行)を ご紹介するものです。
著者の許諾と協力を得て、ウェブサイト『日曜社会学/エスノメソドロジー番外地』内に設置されています。 本書については 下記のページにも著作紹介があります。 ■出版社の紹介ページ ■エスノメソドロジー・会話分析研究会の紹介ページ |
|
合評会・研究会、そのほか著者の動向
社会学者小宮友根の全国行脚。各地で行われる合評会や 著者が報告・参加する研究会などの情報を掲載します。
2014年03月01日(報告@東海大学)
社会学研究互助会
- シンポジウム「概念分析の社会学」準備研究会第一回。
- 日時: 2014年03月01日(土)午後
- 場所: 東海大学(会場は研究会MLにて告知されます)
- 報告者: 植村玄輝(日本学術振興会、哲学)、村井忠康(お茶の水女子大 非常勤講師、哲学)、小宮友根(明治学院大学社会学部付属研究所研究員、社会学)
2013年03月20日(合評会@上智大)
社会学研究互助会
- 『実践としてのジェンダー』合評会。
- 日時: 2013年03月20日(水・祝)13:00~
- 場所: 上智大学(会場は研究会MLにて告知されます)
- 評者: 池田 弘乃さん(都留文科大学ほか教員、法哲学・ジェンダー/セクシュアリティと法)、 毛利 康俊さん(西南学院大学法学部教員、法哲学)
2012年12月27日(報告@京都大)
ジェンダー研究会
- 『実践としてのジェンダー』に関わる研究報告。
(主催者からの詳細告知は11月の予定) - 日時: 2012年12月27日(木)16時半~
- 場所: 京都大学 文学部校舎1階 第2講義室 [キャンパスマップ]
- 問い合わせ先: oda.akiko.62x[at]st.kyoto-u.ac.jp
2012年12月09日(スピーチ@早稲田大)
2012年西尾学術奨励賞授賞式(in 第10回ジェンダー法学会学術大会総会)
2012年11月03日(報告@札幌学院大)
第85回 日本社会学会大会 招待講演
- 講演: 小宮友根「実践の中のアイデンティティ」
- 日時: 2012年11月03日(土)
- 場所: 札幌学院大学
- 日本社会学会 大会情報ページ

2012年06月06日(@web)
Wikipedia - 会話分析
- 2007年にエントリーした Wikipedia「エスノメソドロジー」
 の項目に続いて、「会話分析」の項目をエントリーしました。今回は、NHKスペシャルに取材協力した研究チームの有志との共同執筆です。
の項目に続いて、「会話分析」の項目をエントリーしました。今回は、NHKスペシャルに取材協力した研究チームの有志との共同執筆です。
2012年05月26日(@TV)
NHKスペシャル「未解決事件file.02 オウム真理教」
- 2012年5月26日放送の上記番組に、教団内部の音声テープの会話分析をおこなった西阪仰さん
 の研究チームの一員として出演しました。
の研究チームの一員として出演しました。
- NHKオンデマンドで視聴できるようになりました: 第1部
 第2部
第2部 第3部
第3部
- 「暫定報告書」が公開されました(2012年6月8日): 西阪 仰「NHKスペシャル「未解決事件file.02 オウム真理教」に寄せて」

- 番組放映前のツイートのまとめ: 「オウム真理教」の会話分析

- NHKオンデマンドで視聴できるようになりました: 第1部
2012年03月25日(@東京)
哲学研究会 合評会
- 評者
- 植村恒一郎さん(群馬県立女子大学 文学部教員、哲学)
東京都内にて 15:00-18:00。(要事前申込。連絡・問い合わせは 植村さん t-uemura[at]vmail.plala.or.jp まで)
2012年03月03日(@東京)
2012年02月19日(報告@大阪府大)
社会構築主義の再構築プロジェクト研究会(略称RSC研)
大阪府大ジェンダー研究センター 合同研究会
- 報告: 小宮友根「パフォーマティヴィティの経験的探求の可能性」
- コメンテーター: 伊田久美子(大阪府立大学)
- 司会: 樫田美雄(徳島大学)
2012年01月08日(報告@同志社大)
法社会学会関西支部例会
- 報告: 小宮友根「法社会学における『社会生活の科学』の可能性」
(詳細は法社会学会 までお問い合わせください。)
までお問い合わせください。)
2011年12月03日(コメンテイター@東京大)
社会構築主義の再構築プロジェクト研究会(略称RSC研)
「ドロシー・スミスの『制度のエスノグラフィー』の社会探究法としての射程」
- 報告:
- 上谷香陽(立教大学・非常勤)「ドロシー・スミスにおける『社会的なもの(the social)』の論じ方─『フェミニスト社会学』とIE─」
- 中河伸俊(関西大学)「人びとの社会学としての『制度のエスノグラフィー(IE)』─紹介、評価、構築主義との対話──」
本書について
本書の狙い、本書で取り組んだ問題についてご紹介します。
本書で取り組んだ課題は、「ジェンダー」という概念で指し示される現象を研究するための、ひとつの視点を設定することです。
この課題は大きく分けて以下のふたつの問いに答えることを目指すことで取り組まれています。 >>続きを開く
A1-1: 性現象の「社会」性をめぐる問い
「ジェンダー」という概念は、私たち人間が「性別」という属性を持つ存在であること(このことに関わる現象をまとめて本書では性現象と読んでいます)の「社会的」な側面に光を当てるために用いられてきました。 では、このときの「社会的」とはいったいどういう意味なのでしょうか。また、どのような意味で理解されるべきなのでしょうか。A1-2: 性現象の「不当」性をめぐる問い
A1-1 の問いは、実はジェンダー概念をめぐるもう一つの問いと密接に関わっています。 すなわち、性現象の評価についての問いです。フェミニズムが性現象の「社会」性が主張してきたのは、 その現象の中に「女性の抑圧」という「不当な」要素が含まれているという評価(価値判断)があってのことでした。 では、A1-1 の問いに答えることは、この「評価」をめぐる問いに対して、どのように関わることになるのでしょうか。A2-1
A1-1 に示した問いに対して、ジェンダー概念のオーソドックスな理解のもとでは、性現象を形づくる原因に「社会的」な要素があるのだ、という答えが与えられます。そこでは「社会的」ということの意味は「後天的」ということとあまり変わりがありません。それに対して本書では、そもそも因果説明の対象となる性現象の同定には、人間の行為やアイデンティティについての理解が含まれるということの重要性を強調しました。人間の行為やアイデンティティには無数の記述可能性があり、それらをどう理解するかということは、それ自体法的・政治的・道徳的実践の中で決まり、争われるものであるという意味で「社会」的な特徴を持っています。それゆえ、性現象の「社会」性は、その因果説明の水準だけでなく、理解可能性の水準で捉えることもできるのです。 行為の理解について上記の点が端的に書かれているのは 1章の p. 29 です。ちなみに 2章 と 3章 は、その視点がそれなりに社会学方法論に根ざしたものであることを示す作業にあてられています。そして、上のような意味での性現象の「社会」性は、社会成員の携わるさまざまな実践を記述することによってしか光を当てることができません。本書の II部 では、行為の理解だけでなくアイデンティティや意思の理解について、そうした実践を記述する試みになっています。 >>続きを開くA2-2
A2-1 は、性現象の成り立ちについての事実的な主張です。それゆえ、そこから性現象の「不当」性について、何か積極的な規範的主張が出てくるわけではありません。けれど、性現象の理解可能性を明らかにすることは、それが「なぜ」悪いと言われてきたのかというその「理由」を詳らかにするために役立ちます。「不当」性の経験もまた、行為やアイデンティティの理解と結びついて生じているものだからです。とりわけ、フェミニズムが(自由や平等といった)リベラリズムの語彙を用いつつリベラリズムを批判してきた歴史を考えるとき、このことは重要になります。本書では、フェミニズムが「不当」だと訴えてきた現象が、「性的自由」「表現の自由」といったリベラルな諸概念のもとで生じる様子を記述しました。 「性的自由」については 5章 p. 212、6章 p. 240、「表現の自由」については 7章pp. 278-280 に結論的記述があります。「ジェンダー」概念の難しさ
「ジェンダー」という概念には独特の込み入った事情があります。一方でそれは「セックス」と対になる概念として- (1)性現象には(生物学的ではない)「社会的」な側面があるのだ
他方でそれは
- (2)この社会で女性が置かれている状況は「悪い」ものであり、それは「社会的」であるがゆえに変えられるものなのだ
にもかかわらずジェンダー概念が(1)と(2)の両方の側面を含みながら使われてきたのは、「女は/男は生物学的に○○なのだから、××すべきだ(××してよい)」という主張に対抗しなければならない位置にフェミニズムが置かれてきたという事情によります。だから(1)と(2)が上手く繋がらないままにジェンダー概念が使われてきたことの責任がすべてその概念を使ってきた側にあるわけではないのですが、それでも(1)と(2)の間に距離があるままにジェンダー概念が使われてきたことは確かなことです。
「セックスもジェンダー」?
こうした事情は、90年代以降ポストモダン・フェミニズムと呼ばれる潮流によってジェンダー概念が少し異なった意味で使われるようになってからも、基本的にはあまり変わっていません。「セックスはつねにすでにジェンダーなのである」というJ. バトラーの有名な言葉が端的に示しているように、そこでは「ジェンダー」は「セックス」と対になる(1)の意味では用いられていません。ではどういう意味で用いられているのか、というのはなかなか理解するのが難しいですが、ひどく単純化して言えば、生物学的知識を含む、性別にかかわる知識のありようが、歴史的・文化的な制約のもとで成立している、というような事態を指して用いられることが多いように思います。
けれど、性別にかかわる知識がこのような意味で「社会的」であると言ったからといって、それが間違ったものになるわけでもなければ、「悪い」ものになるわけでもないという点は変わりありません。何よりこのような、およそあらゆる知識にあてはまるような意味で「社会的」という言葉を使っても、それは当たり前すぎて、少なくともそのままでは、個々の現象を分析するための役には立たないでしょう。
では結局のところ、性現象の「社会」性について考えることは、フェミニズムが訴えてきた女性の状況の「悪さ」を考察することにとって必要のないことであり、そうした規範的考察とは独立に進められるべきものなのでしょうか。
実践の記述:本書の視点
本書は、A2 に示したような視点から、上の問いに否定的に答えようとしています。本書の中心にあるのは、エスノメソドロジー/会話分析でいうところの「レリヴァンス(関連性)の問題」、あるいはルーマンシステム論でいうところの「システム準拠」という考えです。第一に、私たちが男性として/女性として生活しているのは、当然ですが、この社会の中でのことです。そしてその社会生活の中で私たちが帯びるアイデンティティは、「性別」だけではありません。つまり、私たちはつねに男性として/女性として行為しているわけではありません。では、いつどのようなときに、どのような仕方で、私たちは「男性として/女性として」行為したり経験したりするのでしょうか。行為の理解やアイデンティティの帰属にかかわるこの問いは、何よりもまず、社会成員自身にとっての問いです。
第二に、フェミニズムがその不当性を訴えてきた「女性の抑圧」という経験もまた、この社会の中で女性たちが経験してきたものです。そしてその経験は、ほかならぬ「女性として」の経験でもあるでしょう。
そうであるならば、ある現象がいかなる意味で「不当」なものとして経験されているのかを、その経験に即して詳らかにするということは、その現象においていかなる仕方で人びとが「男性として/女性として」行為したり経験したりしているのかをあきらかにすることでもあるはずではないでしょうか。
私たちが「男性として/女性として」生活していることと、そこで「女性の抑圧」という経験が生じていることは、いずれも人びとの実践の産物です。本書はその実践を描くことで、性別の「社会」性についての考察と、フェミニズムが訴えてきた事柄の「悪さ」の考察とを((1)と(2)の関係とは異なった仕方で)あらためて結びつけようとする試みです。もちろん決して十分なものとは言えませんが、「ジェンダー」という概念の持つ難しさにこうした視点から光が当たり、それを解きほぐす手がかりとなるなら、それは本書の意義となるでしょう。
書評情報と反応リンク
書評やコメントなどを見かけた方は ページ管理人(![]() )までご連絡ください
)までご連絡ください
受賞
 ジェンダー法学会
ジェンダー法学会 2012年(第五回)西尾学術奨励賞
2012年(第五回)西尾学術奨励賞 授賞
授賞- ジェンダー法学会誌『ジェンダー法学』10号(2013)に、辻村みよ子選考委員長による「西尾学術奨励賞受賞者選考結果について」、および本人による受賞スピーチ「ジェンダー法学への社会学的アプローチ」の内容が掲載されました。
書評
- 樫村志郎,2013,「書評:小宮友根 著『実践の中のジェンダー』」 『法社会学』
 79, 日本法社会学会, 有斐閣.
79, 日本法社会学会, 有斐閣. - 毛利康俊,2013,「書評:法的実践の経験的記述と概念的思考──小宮友根『実践の中のジェンダー』は法律家に何を見せるか」 『法の理論』
 32,
成文堂.
32,
成文堂. - 馬場靖雄,2013,「書評:小宮友根著『実践の中のジェンダー』」, 『ソシオロジ』
 57(3), 京都大学社会学研究会.
57(3), 京都大学社会学研究会. - (著者によるリプライがついています)
合評会
- 社会学研究互助会第五回研究会「小宮友根『実践の中のジェンダー』合評会」
- 毛利 康俊(西南学院大学法学部・教員)「法の中の社会、社会の中の法 ― 小宮友根『実践の中のジェンダー』は法律家に何を見せるか ―」

- 社会学研究互助会第二回研究会「小宮友根『実践の中のジェンダー』合評会」
- 小宮 友根(日本学術振興会特別研究員)「なぜ「実践の中のジェンダー」なのか」

- 加藤 秀一(明治学院大学 社会学部)「小宮友根『実践の中のジェンダー』へのコメント」

- 中里見 博(福島大学行政政策学類)「小宮友根『実践の中のジェンダー』合評会」

反応リンク
- (2012-02-26) ある貴族による小宮友根(2011)『実践の中のジェンダー』ランニングコメンタリー

- (2011-12-08) 樫村志郎さんのブログ: Shiro's Blog : 法的推論に関する新著2冊

- (2011-09-28) 『実践の中のジェンダー』第一章についての plutain さんのコメント

- (2011-09-27) 江口聡さん(京都女子大学現代社会学部、倫理学)によるランニングコメンタリー

※関連リンク:江口聡さんと小宮友根さんとのやりとり - 1)「ポルノグラフィをめぐる断想。と、やりとり。」

- 2)「ジュディス・バトラー、進化心理学、強制的交尾」

- 3)「行動学的定義・行動と心的メカニズムの同定・記述の下での意図帰属」

- 4)「〈評価的用法/記述的用法〉と概念連関」

- 5)「パフォーマティヴィティ概念の解釈をめぐって」

本書に対するよくある質問
本書に寄せられた質問・疑問・異論・反論・批判などにお応えします。
1章補論(p. 45)に デリダが「意図=志向」の現前というテロス」の表現として批判の的にしたのは(Γ・1)の意図に関する条件である。だが、この条件にギリシャ文字(Γ)が振られているのは、ローマ文字(AおよびB)の条件とはその質が異なるからである。 とありますが、「Α、Β、Γ …」ってあったら、このΑとΒはギリシャ文字なのでは?
J. L. オースティン『言語と行為』の中に次のような記述があります(邦訳 p. 27、原著 p. 15)。
第一の重要な区別は、AとBに属する四つの規則全体と、Γに属する二つの規則との間の区別である。(この区別を明示するために、一方にローマ文字を当て、他方にギリシア文字を当てる。)AとBを大文字表記するとローマ文字とギリシャ文字の区別がつかないので、確かにここの記述は少し奇妙なのですが ともあれこのようにオースティンの著書の中で区別がなされており また重要なのは表記よりも規則の質の違い(AとBへの抵触は「不発」となりΓへの抵触は「濫用」となる)ですから 本書では特にこだわらず表記をそのまま受け入れています。
The first big distinction is between all the four rules A and B taken together, as opposed to the two rules Γ (hence the use of Roman as opposed to Greek letters).
「論理的」という表現が頻出しますが、どういう意味で使っていますか?
オースティンにデリダ、さらにはルーマンが 一冊の本の中で いっしょに取り上げられてるって いったいなんなの?
誤植修正
誤植などに気づいた方はページ管理人(![]() )までお知らせください。
)までお知らせください。
第一刷
| 誤 | 正 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第 章 | ||||
| p. 031 | たしかに、 | → | たしかに、 | 下から5行目 |
| 第 章 | ||||
| p. 059 | どのよう行為 | → | どのような行為 | 1行目 |
| 第 章 | ||||
| p. 250 | 驚異 | → | 脅威 | |
| 文献表 | ||||
| p. 296 | Routladge | → | Routledge | 15行目 |
| p. 298 | 人口知能 | → | 人工知能 | 8行目 |
| p. 301 | 性的自由の対する罪 | → | 性的自由に対する罪 | 2行目 |
| p. 304 | April 19 | → | Februrary 22 | |
| p. 308 | → | Thornhill, R., and Thornhill, N. W., 1992, "The evolutionary psychology of men's coercive sexuality," Behavioral and Brain Sciences 15: 363-421. |
文献の追加 | |
著者について
略歴と業績など。
略歴
- 1977年生まれ。
東京都立大学大学院社会科学研究科社会学専攻博士課程修了。博士(社会学)。
日本学術振興会特別研究員PD(明治学院大学)を経て 2014年から東北学院大学経済学部准教授。
業績
- 共著書:
- 酒井泰斗・浦野茂・前田泰樹・中村和生・小宮友根 編 『概念分析の社会学2─実践の社会的論理』
 (ナカニシヤ出版、2016年)
(ナカニシヤ出版、2016年) - 仲正昌樹 編『現代社会思想の海図』
 (法律文化社
(法律文化社 、2014年)
、2014年) - 酒井泰斗・浦野茂・前田泰樹・中村和生 編 『概念分析の社会学─社会的経験と人間の科学』
 (ナカニシヤ出版
(ナカニシヤ出版 、2009年)
、2009年) - 玉野和志 編 『ブリッジブック社会学』
 (信山社
(信山社 、2008年)
、2008年) - 前田泰樹・水川喜文・岡田光弘 編 『ワードマップ エスノメソドロジー―人びとの実践から学ぶ』
 (新曜社
(新曜社 、2007年)
、2007年) - 最近の論文:
- 「裁判員は何者として意見を述べるか―評議における参加者のアイデンティティと『国民の健全な常識』」『法社会学』79号
 (日本法社会学会 編、有斐閣、2013年)
(日本法社会学会 編、有斐閣、2013年) - 「評議における裁判員の意見表明―順番交替上の『位置』に着目して」『法社会学』 77号
 (日本法社会学会 編、有斐閣
(日本法社会学会 編、有斐閣 、2012年)。
、2012年)。 - 共訳書:
- D. フランシス・S. ヘスター著『エスノメソドロジーへの招待―言語・社会・相互行為』
 (中河伸俊・岡田光弘・是永論・小宮友根 訳、ナカニシヤ出版
(中河伸俊・岡田光弘・是永論・小宮友根 訳、ナカニシヤ出版 、2014年)
、2014年) - エリック・ブライシュ著 『ヘイトスピーチ 表現の自由はどこまで認められるか』
 (明戸隆浩・池田和弘・河村 賢・小宮友根・鶴見太郎・山本武秀 訳、明石書店
(明戸隆浩・池田和弘・河村 賢・小宮友根・鶴見太郎・山本武秀 訳、明石書店 、2013年)。
、2013年)。