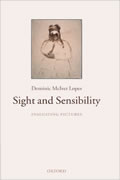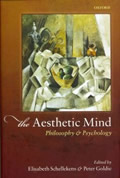002
アリストテレース/
ホラーティウス
(松本仁助・岡 道男 訳)
岩波書店
>>解説文を開く
「美学」とは、ライプニッツ学派に属するバウムガルテンが1735年に提唱した学問である。彼は、「感性」を意味するギリシア語のアイステーシス(αἴσθησις)に基づいて、この学問をラテン語でエステティカ(aesthetica)と名づけた。したがって、この語は語源に即するならば「感性学」を意味する。だが、彼は同時にこの学問を「美の学」とも、「芸術の哲学」とも規定している。すなわち、感性・美・芸術という相互に独立の三つの主題が一つに交わるところに、「美学」が誕生した。ちなみに、「芸術」という概念が成立したのも同じく18世紀中葉である。17世紀の合理主義が18世紀にいたって感性を肯定的に評価し始める。こうした時代思潮が感性学としての美学を可能にしたのである。
だが、アリストテレスの美学、中世の美学といった表現に見られるように、私たちは美学という語をしばしば18世紀以前に投影する。こうした過去への投影も、バウムガルテン自身が古典的な詩学・弁論術を踏まえて美学を構想したことを考慮するならば、決して不当なことではない。実際、古代ギリシアの思想は美学にとっての源泉をなしている。プラトンは『国家』1 において、詩人は理想国家から追放されるべきである、という詩人追放説を唱えた――それは『パイドン』における感性批判、『ゴルギアス』における弁論術批判とも軌を一にする――が、アリストテレスの『詩学』2 はプラトンによる批判から芸術を救い出す試みとして捉えることができる。また、新プラトン主義の創始者プロティノスの論考「美について」3 はアリストテレスを援用しつつ芸術をいわばプラトン主義的に正当化するものであり、歴史的重要性という点ではプラトン、アリストテレスのそれに決して劣らない。
18世紀は「美学の世紀」あるいは「趣味(taste)の世紀」(ディッキー)と呼ばれるにふさわしく、美学上の重要な論考を数多く生み出した。ヒュームの「趣味の標準について」4 は分析系の美学理論によって今なおしばしば参照されており、レッシングの『ラオコオン』5 は、媒体固有性をめぐる議論(グリーンバーグ)や芸術記号論(ランガー、モリス)の先駆をなす。また、18世紀末に公刊されたカントの『判断力批判』6 は、美の無関心性、目的なき合目的性、共通感覚等の概念をとおして、近代美学にその枠組みを与えたにとどまらず、美や芸術をめぐる私たちの思考をいまだに多かれ少なかれ条件づけており、美学における古典中の古典である。
19世紀になると、美・芸術・感性という三つの主題は乖離し始める。芸術の精神化を押し進めるヘーゲルは、『美学講義』7において、美の定義、芸術の発展史、芸術ジャンル論を体系的に描き出す。そして世紀も後半になると、フィードラーのように、芸術は美ではなく認識を目指すと考えて、美学から芸術学を独立させる試みも現れる。彼の「芸術活動の根源」8 は、芸術活動における身体的要素に着目する点で、20世紀後半の現象学的芸術論(メルロ=ポンティ9)とも相通じる。
20世紀の(少なくとも大陸系の)美学理論に決定的な影響を与えたのは、ハイデガーの講演「芸術作品の根源」10 であり、それは芸術作品の存在論への途を開いた。ガーダマーの『真理と方法』11 はハイデガーの立場を解釈学的に人文科学へと解き放った名著である。20世紀後半の思潮を代表する一つに脱構築があるが、これもまたハイデガーの影響下にある。デリダの『絵画における真理』12 は、カントの『判断力批判』を脱構築的に読み解くことで、「近代美学の確立者」といった従来のカント像を一新する。
しばしば大陸系の(伝統的な)美学と分析系の(こうした伝統からいわば断絶したところに始まる)美学は対立的にとらえられる。だが、芸術とは「開いた概念(open concept)」であるというワイツ説(「芸術の定義」の項参照)がアドルノの『美学理論』の基本命題と照応し、また後期ダントーがヘーゲル主義を標榜し、マゴーリスがヘーゲルやフーコーへの共感を隠さない、といった例に見られるように、両者はより密接に関係している。実際、伝統的な美学への参照は、現代の私たちが知らず知らずのうちにとらわれている先入見を相対化する役割をも果たすはずである(この点については小田部胤久『西洋美学史』13 参照)。
なお、日本語で著された美学への一般的入門書としては、佐々木健一『美学への招待』をまず挙げる(同著者による『美学辞典』14 はこの分野での金字塔である)。また、西村清和『現代アートの哲学』15 は現代アートを前に美学することの喜びを読者にもたらしてくれるであろう。(小田部胤久)
いわゆる「美学」の通史や辞典とは異なり、古代から現代までの「芸術」をめぐる思想に焦点を合わせて著された書物。
内容はやや高度だが、たんなる通説や語彙集ではない理論的な「美学入門」として、初学者必携の書。 星野 太(美学/表象文化論、東京大学)
19
ジョセフ・マーゴリス
(森 匡史 訳)
晃洋書房
>>解説文を開く
第2次大戦後新たな展開を見せた現代分析哲学の流れは、わが国でも広範に受けいれられ、現在では哲学・倫理学の分野ではディシプリンとして十分に定着し、優れた研究成果を生みだしている。しかし、こと美学の領域にあっては、わが国において、これまで分析美学が十分に議論されてきたとは言いがたいのが実情である。もっとも英語圏の分析哲学者にしても、1940年代までは美学の領域に関わることには懐疑的であったようだが、50年代以降分析美学は、分析という手法と経験論にもとづいて、18世紀にはじまるヨーロッパ大陸の近代美学とは異なったアプローチで、新たな展開を遂げている。以下に、いくつかのトピックについて、分析美学の主要な論考と、それらが示す大陸の美学とは異なった特徴について概観してみよう。
- 「芸術」の定義 1956年にモリス・ワイツ(“The Role of Theory in Aesthetics” 116)は、芸術はつねに新たなものを生みだす以上原理的に定義不可能だが、その点にこそ芸術の創造的な力があると論じた。しかし、じっさいに伝統的な「芸術」の概念を解体するような20世紀の多様な「アート」が出現するという状況において、それでもなおこれらを「芸術」という語で名指すことの可能性を開いて見せたのは、アーサー・ダントー(「アートワールド」117)である。伝統的な美学は、芸術ないし芸術作品の本質は美と、そこに顕現する人間精神の、それゆえ時代や民族や文化を超えた普遍的な諸価値にあり、それらはいずれも美的対象としての作品のなかに永遠不変に見いだされるものでなければならないとする。しかしダントーは、ある物をアートとするのはそうした永遠不変の「本質」ではなく、特定の時代・民族・社会・文化に広く共有されているアートの理論とアートの歴史についての知識からなる「あるアートワールド(an artworld)」だと主張する。このテーゼは無意味なトートロジーにも見えるが、じっさいには伝統的な美学の根本テーゼを根底から覆す、きわめて野心的な主張である。というのもそれは、芸術を普遍的な価値に根拠づけようとしてきた伝統的な美学に対して、ラディカルな相対主義を突きつけるからである。ダントーの「アートワールド」の概念は、以後、現在にいたるまで、芸術の定義にかかわる論争に決定的な影響をあたえたが、たとえばジョージ・ディッキー(「芸術とはなにか――制度的分析」 218)による芸術の「制度論的定義」もそのひとつである。
- 「作品」の同一性 音楽や演劇のような上演芸術のばあいにつねに問題になるのは、一体「作品」の同一性はいかにして確保されるのかということである。これについても、伝統的な美学の、時代や民族の違いを超えてそれ自体で自立し、自己完結して普遍的な価値を内在させる「作品」というある種のイデア的な観念に対して、分析美学では、ジョセフ・マゴーリス(「芸術作品の同一性」219)のようにタイプ(メガタイプ)とトークンという経験的な概念を用いて論じる立場が主流である。最近では、さまざまなメディアに録音されて流通し、あるいは加工されるロックやジャズ、ポピュラー音楽作品の同一性をどう考えるかについて論じようとするアンドリュー・カニア(“All play and no work: an ontology of jazz” 320)のような議論もある。
物理的には同一性制を保持していると考えられている美術作品のばあいでも、たとえばオリジナルとその(完全な)コピーないし贋作では、美的経験はおなじか異なるのかといったパズルが生じるが、これについてはネルソン・グッドマン(“Art and Authenticity” 421)やマーク・サゴフ(“The Aesthetic Status of Forgeries” 522)らの興味深い論考がある。これらはいずれも作品の美的な質とその同一性を作品に内在する普遍的な質によって確定するのではなく、見る側の「見方」によって変化するものと考えるが、この「見方」には当然ながら当の作品についての歴史的、様式史的知識がふくまれることから、この主張はカント以後の無関心性と形式主義の美学に対するアンチテーゼとなっている。
- 美的経験と批評 「美的(aesthetic)」という語は「一般に「感覚」を意味すると同時に、その中のとりわけ「美や芸術に関わる感性」をも意味するという両義性をになっていて、この意味を確定することは近代美学にとって難問のひとつである。フランク・シブリー(「美的概念」323)はこの難問に、きわめて説得的な議論を提供している。シブリーは、美的用語が指示するある対象の「美的質」――美しいとか繊細だとか情熱的――と、その対象において我々が五感によって客観的に知覚したり物理的に記述できる「非美的特徴」――赤い、滑らか、明るい――とを区別する。その上でシブリーは、対象の美的質は、実際には対象がもつ非美的・感覚的特徴(滑らか)に対して、これを美的に(優美)受けとめる我々の側の「反応」だとする。それゆえ美的質は非美的特徴にあるしかたで「依存している」が、だからといってこの依存関係はいくつかの非美的特徴がそろえばそれに応じた美的質がえられるというようなやり方で「条件的に決定される」わけではない。我々のこの美的「反応」は、我々が生まれつきもっている、その意味で「ある種の自然な」能力であるが、それは一方では社会的な学習の結果でもある。
シブリーのいうように、美的質が我々の側の「反応」であるとすれば、それは我々自身が帰属する特定の共同体に相関的であり、そのかぎりでそれは時代・民族・社会・文化に相対的なものであるだろう。またそれが学習されるものである以上、先に見たサゴフらが主張し、またポール・ジフ(「芸術批評における理由」 424)やケンダル・ウォルトン(「芸術のカテゴリー」 625)も主張するように、それは我々見る側の歴史的、様式史的知識に依存しており、また、作品の美的質に対する我々の側の評価や批評にかんしても、マゴーリス(「芸術作品の評価と鑑賞」526)がいうように、個々人の趣味や判断と、個々人が帰属する共同体におおむね共有された趣味や判断とのあいだのダイナミックな関係にもとづいているというべきである。そしてここでもまた我々は、カント的な無関心性と形式主義の美学に対するアンチテーゼを見いだすことになる。
- 再現と指示(芸術と真理) プラトン以来の伝統にしたがって、芸術は現実の「再現模倣(ミメーシス)」だというならば、作品は現実(さらにはイデア)のたんなる見かけ、18‐19世紀ドイツ美学の用語を使えば現実の「仮象(Schein)」だということになる。しかし近代のとりわけドイツ観念論美学は、むしろアリストテレスにならって、芸術作品こそ現実の現象にひそむ「真理(理念=イデア)」を我々に開示するものだと評価する。そしてこのことは、現代のハイデッガーにおいても変わらない。
だがモンロー・ビアズリー(「視覚芸術における再現」627)がいうように、ひとが「再現(representation)」ということばを使うとき、それはじっさいには「描写(depiction)」と「肖像(portrait)」というふたつのことなった意味で使用されているが、このことをひとはしばしば混同しており、そこから不必要な混乱が生じる。我々が絵画の中に色や線や形からなる特定の「視覚的デザイン」を見て、そこに「ひとりの内省的な男」が再現(模倣)されているというとき、ここでの「再現」は「描写」を意味している。これに対して、そこに描写された「ひとりの男」は歴史上のレンブラント本人を再現しているというとき、これによって我々は、絵画の描写のレベルを超えて現実のレンブラントを「肖像」し、したがって論理的に指示しており、このかぎりでそれは認識的な真理にかかわる。だがこの「肖像=指示」という認識的振るまいは、当の絵画自体には不可能で、この作品にまつわる歴史的事実や証言など、作品外の知識や情報が不可欠である。そうだとすれば、作品がそれじたいで真理にかかわるという主張は、すくなくとも経験的認識にかかわる「真理」概念を前提にするかぎり、誤った主張だということになる。もっともグッドマン(“The Sound of Pictures” 728)やダントー(Transfiguration of the Commonplace 829)のように、作品と現実との関係を独自の「メタファー」という概念でなんとかつなぎ止めようとする立場もある。
上にあげた基本的なトピック以外にも、70年代以降さかんになる環境倫理や環境保護論に呼応するかたちで、伝統的な美学においては軽視されてきた自然美の問題を主題的に論じたアレン・カールソンの論文(“Appreciation and the Natural Environment” 930)に代表されるような環境美学のあらたな動きや、これも伝統的な美学におけるアポリアのひとつであった〈美的〉なものと〈倫理的〉なものとの関係の問題に対して、ダニエル・ジェイコブソン(「不道徳な芸術礼賛」 731)がタイトル通りの大胆な主張で一石を投じることで喚起されたあらたな論争、さらにはジョン・デューイのプラグマティズムを受けついで、いわゆる「芸術」に限定されず、日常生活における美的経験を多角的に論じたアンソロジー(The Aesthetics of everyday Life 1032)やリチャード・シュスターマンの著作(『ポピュラー芸術の美学』1133)に見られるような傾向など、分析美学は現在も多様な論点を提出している。(西村清和)
34
ロバート・ステッカー
(森 功次 訳)
勁草書房
>>解説文を開く
日本語で読める最良の入り口は、ステッカー『分析美学入門』34 だろう。分析美学の多様なトピックを紹介しつつ、最新の論争状況まで丁寧に教えてくれる。まずはここから入って全体の見取り図をつかむのが良いだろう。また、このたび刊行された『分析美学基本論文集』35 は、各トピックの必読文献が日本語で読めるありがたい一冊となった。分析美学に興味がある読者は、この二冊を押さえた上で、興味ある分野の文献に進んでいくのがよいだろう。
単著レベルでの翻訳はまだ遅れているのが現状だが、グッドマンには『記号主義』36 『世界制作方法』37 などいくつかの翻訳がある。またコースマイヤー『美学――ジェンダーの視点から』38 はジェンダー美学の観点から書かれた入門的書物として貴重な存在だ。日本語の書物としては、初期分析美学の状況を伝えてくれる貴重な研究所として、金『美学と現代美術の距離』39 がある。(ここでは合わせて、グッドマン『芸術の言語』40 、ダントー『芸術の終焉以後』41 『芸術とは何か』42 、ウォルトン Mimesis as Make-Believe109 などの重要文献の翻訳が現在進行中であることを紹介しておこう)。
洋書では、まず入門書として Routledge Companion to Aesthetics43 をお勧めする。「芸術の定義」のようなトピックや「グッドマン」「シブリー」などの重要哲学者について、あわせて計62項目をそれぞれ専門家が解説するスタイルで編まれており、改訂を重ねて現在は第3版が出ている。入り口としてこれ以上のものはないだろう。基本論文集(アンソロジー)では、Blackwell社のいわゆる「青本」、Aesthetics and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition44 を挙げておく。若干古くなった感もないわけではないが、収録本数の量・質の点でやはりこれに優るものはない。「分析美学史」の項で挙げられた論文の多くもこれに収録されている。また、トピックごとに対立する論者を並べて論争させるというスタイルの論文集として、Arguing About Art45 と Contemporary Debates in Aesthetics and Philosophy of Art46 がある。どちらも、論争をつうじて議論を発展させていくという分析美学のスタイルをそのまま味わえる刺激的な書だ。最後に、現代の動向を伝えてくれる論文集 New Waves in Aesthetics47 を挙げておく。「創造性(creativity)」「メタ美学(meta-aesthetics)」など、新たなトピックの論文が多数収録されており、分析美学という学問分野がまだまだ拡大・発展していることを示してくれる一冊だ。(森 功次)
地図とは、観光者には見晴らしの良い景色をもたらし、軍人には攻めるべき場所を教え、探検家には未開拓の土地と宝の在り処を示すものだ。
この本は、制作者、鑑賞者にそれらを与えるための地図である。 gnck(美術手帖芸術評論募集 第一席)
ともかくこの充実した目次をみてほしい。その項目のいずれかに心惹かれたなら、それがあなたにとっての美学の入り口となる。各項目の議論状況を第一人者が分かりやすく解説する、美学の見取り図を得るための最適な教科書。改訂に改訂を重ねた第三版。 森 功次(東京大学 美学芸術学 教務補佐員)
>>解説文を開く
芸術の秋だ。だが、いちど芸術作品を離れて、窓の外を見てみよう。紅葉した木々が風に揺れ、秋晴れの青空が広がっている。わたしたちは、このような自然のうちにも、美を見出すのではないだろうか――環境美学(environmental aesthetics)は、芸術作品中心の分析美学では等閑に付されていた自然美を論じる分野として、1960~70年代頃に産声をあげた。
この分野にとって第一に問題となったのは、〈自然についての美的判断は適切であったり、不適切であったりするのだろうか?〉という問いである。環境美学の代表的論者アレン・カールソンは、作者の意図や芸術史の知識を持つことで芸術作品について適切な美的判断ができるのと同じように、自然の場合には常識的/科学的知識を持つことが適切な美的判断のための素地となる、と主張した。環境美学を学ぶならば、まずはかれの主要な仕事がまとめられている Aesthetics and the Environment 48 を一読することが求められよう。ポール・ジフ「芸術批評における理由」24 やフランク・シブリー「美的概念」23、そしてケンダル・ウォルトン「芸術のカテゴリー」25 の仕事を援用しつつ展開されたかれの主張は賛否両論を巻き起こし、環境美学が盛り上がりをみせるための駆動力となった。カールソンに対する批判のうち日本語で読めるものとして、ロバート・ステッカー『分析美学入門』34 第2章がある。ほかに、カールソンに賛意を示しつつその論旨を洗練させようとするグレン・パーソンズの Aesthetics and Nature 49 や、逆に自然についての美的判断に適切も不適切もないという主張を展開するマルコム・バッドの The Aesthetic Appreciation of Nature 50 などもある。エミリー・ブレディの Aesthetics of Natural Environment 51 は自然の美的判断についてその適切さを問うことができるとしつつも、カールソンとは異なる適切さの基準を体系的に示しており、興味深い。このようにさまざまな主張が百花繚乱の様相を呈する環境美学であるが、この分野全体の見取り図を得るためには、カールソンとアーノルド・バーリアントの編集による The Aesthetics of Natural Environment 52 が優れている。環境美学の主要な論稿がバランスよく収められているため、同分野のさまざまな陣営の主張を理解することができるだろう。また邦語文献としては、西村清和の『プラスチックの木でなにが悪いのか』53 を薦める。
第二に、〈自然とも人工物とも確定できない事物について、美学的観点からどのように論じることができるか?〉という問いも重要である。そもそも、われわれにとっての環境とは、ここまでが自然でここからが人工物、というふうに線引きできるものではない。先に挙げたカールソンの著書の目次を眺めてもわかるように、環境美学はいまやいわゆる自然のみを議論の対象としているわけではない。街や建築、環境アートなど、自然と人工のはざまにある事物についても論じている。これらは総じて、芸術作品中心の美学では扱いにくい対象だったと言えよう。自然環境からはじまりこうした多様な対象へと議論を拡大した環境美学から派生するかたちで、日常の美学という分野も生まれた。ユリコ・サイトウの Everyday Aesthetics 54 は、われわれが日常のなかで行っている美的判断について分析的に記し、またそこに含まれうる政治性について丁寧に議論している、この分野を代表する一冊である。また津上英輔『あじわいの構造』55 も、われわれにとって馴染み深い、ノスタルジーや観光、ラジオ体操といった題材を事例として、日常の美学に近しい論点を扱っている。
最後に言及しておくべきは、〈環境美学はいかにして環境倫理学と協働できるか?〉という問いである。実はこの問いは、環境美学にとって本質的な問いである。なぜなら、環境美学が生まれた1960~70年代とは、深刻化する環境問題に対する危機意識や、それに対処しようとする応用倫理学の一分野としての環境倫理学が興った時期にも一致するからである。だが、このふたつの分野は具体的にどのようにクロスするのか。カールソンとシェイラ・リントットの編集による論集 Nature, Aesthetics and Environmentalism 56 は、両分野の関係を考察する論考を中心に編まれている。とりわけこの論集の第1部を見れば、自然の美しさを自然保護の根拠として考える19世紀以来の北米自然思想が環境美学の源流となっていることを理解できる。また、同論集第4部はより現代的な論点として、ランドスケープ・エコロジーと環境美学の関係について扱う論稿を多く含んでいる。ここに論稿が収められているジョアン・ナッサウアーが編集したランドスケープ・エコロジーの論集 Placing Nature 57 をみても、感性の学としての美学が、環境を結節点として、このようなエコロジーの動きと切り離せない関係に置かれていることがわかるだろう。北米自然思想、エコロジーに加えて、環境教育もまた環境倫理学と環境美学とが手を取り合うことを許す領域である。吉永明弘『都市の環境倫理』58 は、とりわけ終章において、都市住民の環境意識を先鋭化させる取り組みにおける美学の関わりを示唆する。(青田麻未)
植物に替えて人工の植物を植えるのは「悪い」こと。自然美をどう捉えれば、この主張は妥当になるのだろうか? 自然の美的な鑑賞に、知識や道徳、倫理はどう関わっているのかを問う表題作をはじめ、環境美学について学ぶための画期的入門書。副田一穂(愛知県美術館学芸員・「芸術植物園」企画者)
「感性を働かせる場」について議論すること、これは美学の社会的使命のひとつである。
言葉づかい、観光、ラジオ体操第一…
さまざまな事例から現代=感性の時代の人々の感じ方を明らかにし、
美学を社会へと開く一冊! 青田麻未(東京大学大学院 博士課程)
059
ルートウィッヒ・ウィトゲンシュタイン
藤本隆志 訳
大修館書店
>>解説文を開く
芸術とはなにか。芸術に関心のある人なら、一度は考えたことのある問いかもしれない。あるいは、自分なりの答えをもっている人も多いかもしれない。もちろん、芸術の哲学としての美学にとっても、これは最重要の問いのひとつだ。少なくとも、「美しい技術(fine arts)」としての「芸術」概念が明確に成立した18世紀なかば以降、数多くの芸術家、批評家、哲学者がこの問いへの答え――芸術の定義――を追求してきた。
1950年代に一石が投じられる。モリス・ワイツ「美学における理論の役割」16 は、同時期に出版されたウィトゲンシュタインの『哲学探究』59 の「家族的類似」の考えを援用して、「芸術はそもそも定義できるような概念ではない」と主張した。ワイツによれば、「芸術」と呼ばれる諸事物は、たんに類似性の網の目でゆるやかに結びついている集まりであって、なんらかの共通の本質を見いだせるようなものではない。分析美学における芸術定義論は、このちゃぶ台返しのような反本質主義への応答として始まった。スティーヴン・デイヴィス Definitions of Art 60 にしたがえば、応答の戦略はおおまかにふたつある。手続き主義(proceduralism)と機能主義(functionalism)だ。
手続き主義者は以下のように考える。たしかに、「芸術」と呼ばれている多様な事物それ自体のうちには、いかなる本質も見いだせないかもしれない。しかし、それらの事物を取り巻く状況に観点を移せば、なんらかの本質を見いだせる。手続き主義はさらに、芸術を取り巻く制度に注目するものと、芸術を取り巻く歴史に注目するものに区別される。制度説を代表するジョージ・ディッキーの記念碑的論文「芸術とはなにか──制度的分析」18 は、そのアイデア元のひとつになったアーサー・ダントーの「アートワールド」論文 17 とともに、『分析美学基本論文集』35 に収録されている。歴史説を代表するジェロルド・レヴィンソンの論文は、青本(Aesthetics and the Philosophy of Art) 44 で読める。
一方、機能主義者は以下のように考える。芸術は、美的機能を果たしているものとして、あるいは美的機能を果たすよう意図されているものとして、適切に定義できる。機能主義には多くのバリエーションがあるが、基本的なパターンは、Theories of Art Today 61 に所収のジェイムズ・アンダーソンの論文を読めば把握できるだろう。典型的な機能的定義を提示しているモンロー・ビアズリーの論文もまた、青本 44 に収録されている。
こうした多様な立場とそれぞれが抱える問題点については、デイヴィスの Definitions of Art 60 とロバート・ステッカーの Artworks 62 がきわめて優れた概観を与えてくれる。よりコンパクトなサーベイとしては、同じくデイヴィスによる The Routledge Companion to Aesthetics 43 の「Definitions of Art」の章を、日本語で読めるものなら『分析美学入門』 34 の第5章をすすめる。
機能主義も手続き主義も、それぞれに難点をもっている。機能主義は、外延的に不適切だとしばしば批判される。つまり、機能主義は、非美的な芸術や美的な非芸術を適切に分類できない。一方、手続き主義のわかりやすい難点は、その循環性にある。つまり、「芸術」をアートワールド(制度であれ歴史であれ)の観点から定義できるとしても、その「アートワールド」をそれ以外の慣習から区別するには、結局「芸術」概念に訴えるほかないようにみえる。たしかに、西洋のいわゆる高級芸術に議論を限定するなら、当のアートワールドの制度と歴史の同定に困難はないかもしれない。そのかぎりでは循環性は問題ない。しかし、デイヴィスがいうように、「芸術」概念を非西洋の芸術やポピュラー芸術にも適用しようとする場合には困難が生じる。結局のところ、手続き主義が特定のアートワールドを超えた一般的な射程をもつためには、アートワールドをほかの社会的慣習から区別するものを特定しなければならない。
こうした膠着状況のなかで、新たな方向がさまざまに模索されている。ステッカー Artworks 62 は、歴史的に変化する機能という観点から芸術を定義する「ハイブリッドな定義」を提案している。ダントーは、「アートワールド」論文ではいかなる定式化された定義も提示していないが、The Transfiguration of the Commonplace 29 では、芸術の本性についての自身の考えをより具体的に示している。このダントーの立場もまた、機能主義と手続き主義のハイブリッドとして解釈できるかもしれない。また、ノエル・キャロル編の芸術定義論のアンソロジー Theories of Art Today 61 には、従来の問題を踏まえたさまざまな立場からの多彩な論考が収録されている。そのうちのひとつ、ベリス・ゴートの論文は、その後いくらかの論争を巻き起こした。ゴートが提唱するクラスタ説は、ワイツのような反本質主義に共感しつつも、「芸術」概念のまとまりの形式と内容を具体的に特定していこうとする立場だ。
哲学的な概念分析から離れて、より経験的なアプローチに訴える動きもある。ハワード・ベッカー Art Worlds 63 は、ディッキーが示した芸術制度というアイデアの内実を社会学的な観点から明らかにしようとしている。デニス・ダットンの The Art Instinct 64 やデイヴィスの最近の著作 The Artful Species 65 では、進化美学的な観点から芸術の本性への接近が試みられている。
さらに、芸術一般の哲学から離れて、個別芸術の哲学へと向かう動きもある。この立場からすれば、われわれは、「芸術とはなにか」と問うよりも、「音楽とはなにか」「建築とはなにか」「映画とはなにか」といったかたちで個々の芸術形式(art form)の本性を問うべきだということになる。ピーター・キヴィの Philosophies of Arts 66 は、この立場を明確に打ちだした論争的な本だ。アーロン・メスキンが論文 「From Defining Art to Defining the Individual Arts」 67 でいうように、個別芸術の定義もまた、反本質主義的な懐疑にさらされるかもしれない。とはいえ、それは、芸術一般の定義よりもはるかに有望かつ有益なものであるように思われる。ドミニク・ロペスの最近の著作 Beyond Art 68 では、まさにこの論点が詳しく論じられている。(松永伸司)
>>解説文を開く
音楽作品の存在論は、分析美学の中でも最も熱い論争が交わされている分野の一つである。現在の議論の源流は、ともに1968年に初版が出版されたリチャード・ウォルハイム Art and Its Objects 69 とネルソン・グッドマン Languages of Art 40 にさかのぼることができるが、近年の分析形而上学の展開や、西洋芸術音楽以外の多様な音楽実践への注目とともに、非常に広範な論点が提起されている。
美学者のみならず、多くの哲学者が参加しているのが、音楽作品の存在論的性格をめぐる論争である。音楽作品が属する存在論的カテゴリー、持続条件、個別化条件などがここでは問題となっている。二つの重要な文献を紹介しよう。2000年代の存在論論争の発端を作ったと言えるジュリアン・ドッドは、Works of Music 70 において、音楽作品は演奏により反復される、音楽作品は聴取できるという日常的直観に議論の起点を置き、音楽作品を音出来事タイプとみなす見解を擁護している。ドッドの同書は自説の展開とともに有力な諸立場のサーヴェイとそれへの反論から成り立っており、論争状況を知るためにも格好の一冊である。ドッドの批判対象の一つでもあるデイヴィッド・デイヴィス Art as Performance 71 は、音楽作品とは「生成的パフォーマンス(generative performance)」である作曲者の作曲行為だと主張している。デイヴィスの議論は芸術作品の鑑賞、美的性質に関する考察から出発しており、シブリー「美的概念」23 や Walton, “Categories of Art” 25 と密接に関連する。現在の主要な論点を知るには、音楽作品に特化したものではないが、クリスティ・マグワイアが編集した Art and Abstract Object 72 がよい。音楽作品が分析形而上学の中でどういう位置を占めているのか、音楽作品の存在論の射程と奥行きを知ることができるだろう。邦語文献としては、倉田剛「芸術作品の存在論」(西日本哲学会編『哲学の挑戦』所収)73 が、タイプという存在論的カテゴリーの特徴を描き出すとともに、著作権や存在論の方法論など多様な観点から考察を試みており大変参考になる(倉田は『現代形而上学』74 の中の二つの章で、人工物とその特徴である存在依存について詳しく論じている)。
音楽実践やそこで用いられる諸概念の詳細な分析も、音楽作品の存在論が取り組んできた課題である。とりわけ非西洋芸術音楽を対象とする存在論的考察では、この側面が顕著である。スティーヴン・デイヴィス Musical Works and Performances 75 における「スタジオ・パフォーマンス(studio performance)のための音楽作品」と「ライブ・パフォーマンス(live performance)のための音楽作品」の区別、あるいは「厚い(thick)作品」と「薄い(thin)作品」の区別の導入などは、その典型例である。増田聡『その音楽の〈作者〉とは誰か』76 ではクラブ・ミュージックにおける作品概念が詳細に分析されており(第2章)、この分析をめぐって近年でもワークショップが開かれるなど、盛んに議論がなされている。
冒頭で述べたように、音楽作品の存在論は、分析美学の中でも最も熱い論争が交わされている分野の一つである。しかし同時に、音楽作品を存在論という枠組みで論じることについても多くの疑問と批判が提起されてきた。すなわち、「存在論的に音楽作品を問うこと」の意義と価値は何であるのか、そのこと自体が大きな論争となっているのである。批判の中で大きな影響を今なお持ち続けているのが、1992年に出版されたリディア・ゲーア The Imaginary Museum of Musical Work 77 だ(第1章の翻訳が福中冬子訳・解説『ニュー・ミュージコロジー』78 に収められている)。その中でゲーアは、西洋における「音楽作品」概念の歴史性と各時代における音楽実践の諸相を明らかにしながら、存在論的性格をめぐる分析美学的議論がそうした歴史性を軽視していると批判する。(田邉健太郎)
『月光』いたるところで演奏されるが、では当の音楽作品はどこにあるのか。
別人が知らずに書いた一言一句そっくりの文学作品は同じ作品か。
こうした謎を考えるうちに、あなたはいつのまにか形而上学の世界にいる。
あなたには地図が必要だ。 鈴木生郎(現代形而上学、慶応義塾大学)
80
ウィリアム・G・ライカン
(荒磯敏文・川口由起子・鈴木生郎・峯島宏次 訳)
勁草書房
>>解説文を開く
かつて言語哲学は分析哲学の中心地だった。70年代頃までは、言語哲学は哲学の方法論と中心的な問題を提供し、哲学にとって特権的な位置を占めると考えられることも稀ではなかった。日本でも、ひょっとするといまだに分析哲学イコール言語哲学と思っている人もいるかもしれないが、少なくともそのイメージは現状にはそぐわない。現在の言語哲学は、分析哲学の大きな分野のひとつではあるが、科学哲学・美学・形而上学・認識論といった多くの分野のうちのひとつ以上のものではない。こうした歴史については、飯田 隆『言語哲学大全』79 に当たるのがよいだろう。このシリーズは分析哲学全体の入門としても非常に優れた著作だ。
以上のような事情もあって、美学と言語哲学の関係は入り組んでいる。(1)美学の中で言語哲学的な方法論やアイデアが活用される場面、(2)美学的な主題が言語哲学の中で扱われる場面にわけて説明しよう。
- (1)美学の中の言語哲学的な方法論
- かつての分析哲学にとって、言語を分析するというアプローチは得意分野だったため、初期の分析美学者たちも、言語の分析を通じて美学の問題にアプローチしようとした。特に日常言語学派の影響は大きい。分析美学基本論文集の中で言えば、シブリー「美的概念」23 の美的述語の分析や、ジフ「芸術批評における理由」24 やマゴーリス「芸術作品の評価と鑑賞」26 の批評言語の分析にそれを見られるだろう。現代ではこの傾向は薄れたが、それでも言語哲学がコミュニケーションや表象に対する重要なアイデアの源泉であることは変わらない。例えば作品解釈を考える上でグライスやデイヴィドソンのような言語哲学のアイデアは有用になる(「意図と解釈」の項目を参照)。ただし、言語哲学は、現在でも発展がはげしい分野だ。言語哲学や言語学の知識をアップデートすることは、美学の問題を考える上でも役に立つ。現代的な言語哲学の入門には、ライカン『言語哲学』80 、言語学の入門にはアラン・クルーズ『言語における意味』81 、特に哲学と関係の深い形式意味論の入門にはポートナー『意味ってなに?』82 がよいだろう。
- (2)言語哲学の中の美学的な主題
- 一方、美学的な主題が言語哲学の中で扱われることもめずらしくはない。その典型例がフィクションだ。フィクションを巡る語りは指示や意味論の限界事例として刺激的な議論の場となってきたし、フィクションは美学者と言語哲学者がともに関心をもつホットな領域だ(「フィクション」の項目を参照)。
またメタファーのように、それ自体「美的」な言語現象もある。分析哲学における比喩論についてはライカン『言語哲学』の「メタファー」の章が参考になるだろう。なお、この分野は日本でも紹介が進んでおり、佐々木編『創造のレトリック』83 、デイヴィドソン「隠喩が意味するもの」(『真理と解釈』)84 などで主要な論文のいくつかを読むことができる。また認知言語学の創始者レイコフと哲学者マーク・ジョンソンによる比喩論の古典『レトリックと人生』85 にも翻訳がある。
また、「おいしい」「たのしい」といった趣味判断の言明も実は現代の言語哲学でホットな領域となっている。激しい議論を呼んでいる「意味論的相対主義(semantic relativism)」の主要な提唱者マクファーレンのついに出た単著 Assessment Sensitivity 86 は言語哲学の著作だが、趣味に関する言明にはいかなる意味があるのかという問題を扱っており、メタ美学の問題を考える上でも重要な一冊だろう。(高田敦史)
096
Gary Iseminger (ed.)
Temple University Press
>>解説文を開く
白いドレスを纏った女性がパラソルをさして佇んでいるように見える絵画を前にして、その作者から「ヘラクレスを描いた絵だ」と説明されたならば、私たちはその絵画をどのように見ればよいのだろうか。作者の言葉を信じて、なんとかそれがギリシア神話の英雄ヘラクレスであると考えられるような理屈を捻り出すべきだろうか。作者の言葉を無視し、見えるがままに受け取るべきだろうか。これは極端な例ではあるが、多かれ少なかれ、私たちは作品を理解する際に、作者の意図をどのように処理すべきか判断を下さねばならない。
作品解釈と作者の意図との関係に関するこのような問題は、分析美学における主要なトピックのひとつとして議論されてきた。もちろん、解釈(interpretation)については一般解釈学を目指すシュライアーマッハー、ディルタイ、ガーダマー(『真理と方法』11)といった哲学的伝統があり、また、意図(intention)についても分析哲学、特に行為論において、アンスコム『インテンション』87、ブラットマン『意図と行為』88、デイヴィッドソン「墓碑銘のすてきな乱れ」89などによる考察がなされてきた。それらの議論を参照することは、ここでの問題にとってヒントを与えてくれるだろう。しかし、分析美学における意図と解釈の議論はあくまでも芸術作品に焦点を絞っており、その核心には、〈芸術の自律性〉という観念があることを忘れてはならない。
〈芸術の自律性〉という考えは、この議論の発端となったウィムザット&ビアズリーによる論文 “The Intentional Fallacy” 90 の強い動機となっている。ニュークリティシズムに与する彼ら(この辺りの関係は、Literary Theory and Criticism 内の “The New Criticism” および “The Intentional Fallacy” の項目91 を参照するとよいだろう。日本語文献としては、『現代批評理論のすべて』92 を挙げておく)がそこで主張したのは、作者の意図は作品の解釈や評価に使用できないし、使用してはならないということだった。反意図主義(anti-intentionalism)と呼ばれるこの立場は、一見すると、フランスにおいてロラン・バルトが主張した「作者の死」93 に類似しているようにもみえるが、読者による創造性を重視したバルトとは違い、ウィムザット&ビアズリーは、“The Affective Fallacy” 90 において読者からも作品を切り離している点で、より徹底している。
これに対して、ハーシュの Validity in Interpretation 94 を皮切りに、意図を重視すべきとする意図主義(intentionalism)からの反論が相次いで起こった。意図主義者は、〈ともに妥当であるが両立不可能な複数の解釈〉がある場合に、作者の意図を参照することによって、そのなかから唯一の正しい解釈を決定することができるという利点がある。しかし、それは他方で、作者の意図さえ知ることができれば、作品そのものは必要ないということになりかねない。こういった危険を避けるために、穏健な意図主義(moderate intentionalism)と呼びうる、主にステッカー『分析美学入門』34 やキャロルらがとる立場が登場する。そういったなかで、クナップ&マイケルズは “Against Theory” 95 において、作品の意味と作者の意図とを完全に同一視する方向へと進んだ点で異彩を放っている。
1992年に刊行された論文集 Intention and Interpretation 96 は、過去の主要な関連文献を再録しつつ、刊行に合わせて気鋭の論者によって書き下ろされた論文を含んでおり、意図と解釈に関する議論を概観できるものとなっている。そのなかでも、この論集全体の総括となっているレヴィンソンの論文(のちに「文学における意図と解釈」97 として改稿される)は、意図と解釈の問題に関する問題点を整理しただけではなく、意図主義と反意図主義に対する第三の選択肢として、仮想意図主義(hypothetical intentionalism)という立場を打ち出した点で重要である。以降、意図と解釈をめぐる問題は、特に仮想意図主義と穏健な意図主義との間で活発に議論されている。
各論者は、意図主義、反意図主義、仮想意図主義といったいわば縦糸の間で多様な立場をとっているが、その違いは意図と解釈をめぐる様々な課題をどのように取り扱うかという横糸と関わってくる。ここでは最後に、それらの課題のいくつかについて簡単に見ておこう。
- 参照の範囲に関する問題:テクスト以外にはなにも参照しない反意図主義を一方の極におき、他方の極に作者の意図までも参照する意図主義をおくならば、その間には、作者についての情報、作品成立の時代背景、芸術や言語に関する慣習などといった諸段階があり、それらのうち、どこまでを正当な根拠として認めるかによって立場の違いが生じる。
- 一元主義と多元主義に関する問題:基本的に、意図主義は、唯一の正しい解釈を決定できることを利点として挙げ、反意図主義は複数の正しい解釈があるという現状の説明に適していると主張する。ただし、バーンズ On Interpretation : A Critical Analysis 98 は意図主義の観点から複数の解釈の可能性を説明しようとしているし、ネハマス “The Postulated Author; Critical Monism as a Regulative Ideal“99 は仮想意図主義に近い立場から一元主義を擁護している。
- アイロニーに関する問題:ある事柄を述べながら、その反対の意味を示すアイロニーは、テクストのみに基づく反意図主義に対する決定的な反論としてしばしば言及される。例えば、「穏健なる提案」100 と呼ばれるスウィフトのエッセイがあるが、反意図主義の流儀でそのテクストを字義通りに理解するならば、1歳の赤児を食肉として流通させることで貧困と食糧問題を解決できるという提案として読める。もちろん、意図主義者は、作者の意図を参照することによって、これがアイロニーであることがわかると主張するだろう。しかし、文脈や作者の他の作品を参照すれば十分である、あるいはテクスト自体からのみ判断できると主張することも出来る。
これらと関連して、例えば意図を参照することでアイロニーの問題を解決する場合、パラフレーズの問題(つまり、作者の意図を知れば、作品そのものが不要となる)や、アイロニーの持つ二重性を無視してしまう問題が生じるし、そもそも作者は作品を自律的なものとして意図して作ったという〈意図主義のパラドクス〉101 などもあり、多様な問題が絡み合いながら、意図と解釈をめぐる議論は展開している。
いずれにせよ、意図と解釈をめぐる問題について興味をもったならば、まずは邦訳されているステッカー『分析美学入門』34 第7章「解釈とそこに関わる意図の問題」、レヴィンソン「文学における意図と解釈」97 から読み始めるのが良いだろう。芸術における意図と解釈のみを主題とした著作は多くはないが、リヴィングストン Art and Intention 102 は比較的新しく充実した仕事となっている。また、美術史家の観点から書かれたものとしてバクサンダール Patterns of Intention 103 を最後に挙げておきたい。(河合大介)
>>解説文を開く
意外に思われるかもしれないが、分析哲学の伝統ではフィクションは人気のあるテーマだ。その歴史は長く、テーマとしても広範囲にわたり、美学の範囲だけにおさまるものでもない。もともと分析哲学の伝統でフィクションが問題になったのは、それが真理・指示・存在といった重要な概念の限界事例だからだ。例えば、私たちはシャーロック・ホームズという人物が存在しないことを知っていても、「ホームズはロンドンに住んでいる」といった発言を真と見なす。もし真なる文が何らかの事実を表現するものなのであれば、〈ホームズはロンドンに住んでいる〉といった何かしらの事実が実現しており、ホームズはその事実の構成要素であり、従って存在するものでなければならない。もちろんこれはありうる発想のひとつでしかないが、これを検討しはじめることは、すでにフィクションを巡る哲学的問題の沼に一歩足を踏み入れることだ。
こんな風に指示や真理といった意味論的概念から存在の問題にアプローチすることは分析哲学の伝統の中では、非常によく親しまれた方法だ。特に、分析哲学のマスタピースであるクリプキの『名指しと必然性』104 は、名前の指示についてそれ以降の議論を強く規定した一冊であり、フィクションの哲学を考える上でも避けては通れない。藤川直也『名前に何の意味があるのか』105 は、クリプキ以降の名前に関する現代までの論争をクリアにまとめ、クリプキの立場をより洗練させた立場を擁護している。特に、6章ではフィクションのキャラクター名に関する問題が中心的に扱われている。本書を読めば、名前と存在を巡る哲学的問題の中でなぜフィクションが哲学の問題になるのかについて、明確な地図を描けるだろう。
また、アミ・トマソンの Fiction and Metaphysics 106 はキャラクターの存在論で重要な一冊である。トマソンは、フィクショナルキャラクターは文学的創作物であり、法や言葉などと同じ、人間が作り出した抽象的人工物(abstract artifact)であり、それゆえ存在者の一員であるという立場をとっている。これはキャラクターの存在や同一性を考える上で、現在では避けて通れない一冊になっている。また、やや古いが、三浦俊彦『虚構世界の存在論』107 は日本語で、フィクショナルキャラクターの存在論の詳細なレビューを与えている。また、キャラクターの存在論の主要な立場のひとつであるマイノング主義の代表的な哲学者のひとりプリーストの『存在しないものに向かって』108 にも翻訳がある。
もちろん、指示や真理や存在だけがフィクションの哲学の重要なテーマではない。例えば美学者はフィクションとは何かという問題に関心を持ってきた。この領域で特に重要なのは、ケンダル・ウォルトンの Mimesis as Make-Believe 109 だ(手っとりばやくウォルトンのフィクションに関する立場を知りたければ、『分析美学基本論文集』収録の「フィクションを怖がる」110 を参照)。ウォルトンは子どものごっこ遊び(メイクビリーブ)をモデルに、フィクション、ひいては表象芸術一般についての統一的な理論を展開している。ウォルトンの立場はフィクションを一種の想像のゲームとして捉えるもので、そこでメイクビリーブはフィクションを特徴づける特殊な心的態度(何かを真であると信じること(信念)と対比される)として位置づけられる。サール 『表現と意味』111 における「主張のフリ」説とともに、フィクションをフリやごっこといった特殊な態度・発話行為と捉えることは現在では主流の立場となっている。また、グレゴリー・カリーの The Nature of Fiction 112 もメイクビリーブのアイデアを使い、ウォルトンに近い立場を擁護している。
邦語文献では、清塚邦彦『フィクションの哲学』113 はウォルトンに共感的な立場から、フィクションとは何かを議論している。西村清和『フィクションの美学』114 は、主として美学的な関心から、フィクションと感情を巡る哲学的問題などを扱っている。また、美学的なフィクション論については、ステッカー『分析美学入門』34 の8章でまとまった解説を読むことができる。
セインズブリーの Fiction and Fictionalism 115 はフィクションの哲学の教科書として読めるものであり、上記で触れたほとんどすべての分野を扱っている。特に、道徳や抽象的対象は一種のフィクションだとする立場(虚構主義)についても詳しく触れているのは本書の長所だろう。
またエイリーン・ジョン、ドミニク・ロペスの The Philosophy of Literature 116 は、フィクションと文学の哲学の代表的な文献を集めたアンソロジーであり、英語圏のフィクションに関する重要論文のほとんどが収録されている。(高田敦史)
Q「キャラクターってなんだ」
A「抽象的人工物であり、文学的創作物」←トマソンの答え
形而上学的キャラクター論の最高峰! キャラクターの存在、同一性、カテゴリー…etc.の問題に答えます。 高田敦史(会社員)
121
Gregory Currie
Oxford University Press
>>解説文を開く
物語(narrative)は小説、映画、マンガ、歴史などを含む幅広いカテゴリーだ。簡単には、複数の出来事の連鎖を語り、「ストーリー」があると言われるようなものはすべて物語と呼ばれる。フィクションとは区別される概念で、歴史やジャーナリズムなど典型的なフィクション以外のものも含む。
物語の哲学は、かつては歴史の哲学の一部として盛んに論じられた。アーサー C.ダント『物語としての歴史―歴史の分析哲学』117 や野家啓一『物語の哲学』118 は、主として歴史哲学の観点から物語を扱うものだ。そこでは、物語を、過去の出来事を未来の出来事との関わりから捉えるものと捉えた上で、そこには何が含まれているのか、物語的記述はつねに過去を歪めてしまうものなのかといった問題が論じられる。
また複数の出来事を束ねる物語的同一性は、人の同一性、人生の価値、自由といった哲学的問題にも示唆を与えてきた。自己を過去から未来へと時間的に持続するものと捉えることは、自らをひとつの物語として構成するという側面を含んでいる。こうした発想は「物語論的アプローチ」と呼ばれ、倫理学や形而上学のみならず、哲学外でもしばしば流行のテーマとして扱われてきた。マッキンタイア『美徳なき時代』119 は、自己の構成を物語として捉える代表例だ。また信原幸弘、太田紘史篇『シリーズ 新・心の哲学II 意識篇』120 にも物語的自己論を含む自己論のサーベイ論文が収録されている(福田敦史「自我性を求めて──物語的自我・現象的自我・脳神経科学」)。
これら歴史哲学の物語論や自己論としての物語論は、「物語」を他の哲学的問題のための説明のツールとして用いるアプローチと言えるだろう。一方近年の分析美学では、物語を独自の表象の形式と捉え、芸術哲学的な観点から物語とは何かを扱う研究が増えている。こちらは表象形式としての物語そのものを分析対象とするアプローチだ。グレゴリー・カリーの Narratives and Narrators 121 は、物語の定義からはじまり、語り手の人称や視点の問題など、古典的な物語論のテーマも受けつぎつつ、体系的な物語論を展開している。また、ノエル・キャロル篇の The Poetics, Aesthetics, and Philosophy of Narrative 122 は美学のトップジャーナル Journal of Aesthetics and Art Criticism の物語特集号を書籍化したものだ。ストーリーの同一性、画像における物語、物語への共感など多様な論点が扱われている。また、こうした議論では、ジュネットやチャトマンなど、文学理論における古典的な物語論が(ときに批判的に)参照されることも珍しくない(『物語のディスクール』123、『小説と映画の修辞学』124)。物語を巡るさまざまな概念・事象の整理という点では両者の関心は一致しているからだ。
これら文学的・芸術哲学的な物語論と、前述の歴史哲学や自己の物語論との間の議論はまだ盛んであるとは言えないが、今後発展が期待される領域だろう。(高田敦史)
132
Dominic M. Lopes
Oxford University Press
>>解説文を開く
描写(depiction)の哲学(画像表現の哲学)は、画像(picture)(絵、写真)とはどんな表象(representation)なのかを問う分野だ。画像が何らかの情報を伝えることはごく常識的な発想だが、ではどんな情報をどんな形で表現するのか? 何がそれを可能にするのか?
邦語文献だけを見ていてもわかりづらいが、描写の哲学は、ここ10年ほどの分析美学の中でも特に発展した領域だ。ここ数年以内に書かれた英語の論文と10年以上前の論文を比較して読んでみれば、そのちがい(用語法の厳密さや論点の整理のされ方)に驚くだろう。現在の描写の哲学は、言語哲学や知覚の哲学のような、よく言えば専門的で発達した領域に、悪く言えばいささか細分化しすぎて手を出しづらい領域になりつつある。しかしいずれにせよ、そこには豊富な成果がある。
美術史家ゴンブリッチの一連の論考(『棒馬考』125など)は画像表現論の古典であり、現代の研究でも諸説の検討はまずはここからはじまる場合が多い。また、絵画の分析哲学といえば、グッドマンの『芸術の言語』 40が有名であり、この本は耳にしたことのある人も多いだろう。ところが、これらの古典は、正直に言えば、「生きている」本ではない。歴史研究をのぞいて、グッドマンが直接に参照されることはずいぶん少なくなった(言うまでもなく、古典は何度も復活するものであり、その点で『芸術の言語』も例外ではないが)。ただし何が画像表象を可能にするのかといった論点や、他の表象形式との比較を重視するスタイルはこれらの古典が形成した土台でもあり、現在の研究にも共通するものだ。
研究の力点も移っている。古典的な描写の哲学の主題はあくまでも芸術としての絵画や写真だった(これについては、例えば『分析美学基本論文集』のビアズリー「視覚芸術における再現」27を参照)。現代の美学者の多くは、芸術としての絵画と画像表現の本質は明確に区別する。描写の哲学の主要な対象はまずは後者であり、絵画にかぎらず、教科書の図、政治ポスター、証明写真などあらゆる画像が問題にされ、それらが共通して実現している「画像表現」とはいかなる種類の表象であるのかが問われる。
ロペスの Understanding Pictures 126 はこの現在の研究状況を作った一冊だ。それ以前の描写の哲学に関する諸説を明確にまとめ、心の哲学などの最先端の研究を参照した上でオリジナルな立場を擁護している。古典的な描写の哲学の諸説は今から見ると非常にわかりにくい部分も多いのだが、ロペスの整理や批判は非常に明確なものになっている。またドレツキやエヴァンズに影響を受け、画像を情報の流れの一部として位置付ける発想もそれ以前とは一線を画すものだ。カルヴィッキの Images 127 は最近の教科書であり、描写に関する諸説を比較検討しており、先行研究の紹介は非常に丁寧だ。また「心的イメージ」や科学で用いられるグラフなど、狭義の画像におさまらないイメージも扱っており、幅広い関心に答えてくれるだろう。アベル、バンティナキによる Philosophical Perspectives on Depiction 128 は現在の研究水準を知ることができる新しい論文集である。多くの論者は心理学などの成果も参照しつつ、画像表現の問題に取り組んでいる。最近の研究の全体像が知りたい読者はこの3冊にあたるのがよいだろう。
また描写の哲学は、実は知覚の哲学とも関連が深い。知覚と画像はどちらも典型的な非言語的表象、広い意味での「イメージ」を扱う分野だからだ。知覚の哲学に関しては近年翻訳されたフィッシュ『知覚の哲学入門』 129 がよい手引きとなってくれるだろう。また日本語で絵画表現を扱った美学の文献として西村清和『イメージの修辞学』130 があり、描写と知覚の哲学を橋渡ししてくれるであろう小熊・清塚編『画像と知覚の哲学』131 も刊行予定となっている。
最後に、ロペスの Sight and Sensibility 132 は現代的な描写の哲学をふまえた上で、改めて芸術としての絵画を扱った著作だ。そこでは、絵画の美を軸に、絵画の芸術的価値と認知的価値・道徳的価値の関係や、感情表出などの技法が論じられる。また、それ自体としては美しくない光景が、絵画を通して描かれたときに美しい光景となるのはなぜなのか?(ミメーシスのパラドックス)といったユニークな美学的問題が検討される。描写の哲学の向こうにある新たな絵画論の可能性を教えてくれる著作だろう。
(高田敦史)
肉眼では見えない光景。
画像の中だけにある美しい光景と、どうしてそんなものがあるのかについて。画像の美と可能性を擁護する現代美学の最良の絵画論。 高田敦史(会社員)
絵ってそもそもなに? イリュージョン? 記号? いうても対象に似てるよね? 絵とグラフはどう違う? 絵と写真は? 科学における図の役割は? 「絵がリアル」ってどういうこと? こんな問いに関心があるなら、まずはこの本をどうぞ! 〈描写の哲学〉最新最強の入門書!! 松永伸司(美学/ゲーム研究)
141
Aaron Meskin & Roy T. Cook (eds.)
Wiley-Blackwell
>>解説文を開く
美学は芸術の哲学だった。フランク・シブリー「美的概念」23がいうように、美的なものを論じるかぎりでは、本来その対象は芸術である必要はない。しかし歴史的にみれば、美学は芸術の哲学として展開してきた。そしてそこであつかわれる「芸術」は、いわゆる高級芸術(high art)にかぎられていた。「現代美術」や「現代音楽」や「アヴァンギャルド」などといっても、その文脈はつねにファインアートであり、クラシックであり、アートワールドだった。ピエール・ブルデュー『ディスタンクシオン』133のような社会学的なアプローチを除けば、この傾向は、大陸の美学にも日本の美学にもいまだにはっきりとみられるものだろう。
しかし、美的な問題が重要なかたちでかかわる人工物は、高級芸術だけではない。むしろ、20世紀から21世紀にかけて産業的に大きく発展すると同時に美的に高度に洗練されていったのは、従来「低級(low)」とされてきたたぐいのポピュラー文化である。1990年代以降の分析美学のひとつの流れは、ポピュラー文化の諸形式の少なくとも一部を美学の対象として――つまりそれぞれを一個の芸術形式(art form)として――正当にとりあげようというものである。この「ポピュラー芸術」には、たとえば、ジャズやロックといったポピュラー音楽、コミック(アメリカンコミック、バンドデシネ、日本のマンガを含む)、映画、アニメーション、ビデオゲームなどが含まれる。
もちろん、美学のなかには「低級芸術」あるいは「娯楽」に対する反感が伝統的に根強くあったし、おそらくいまでもある。そこでなされる非難の定型は、「紋切り型である」、「受容者に能動性を与えない」、「無関心性を欠く」といったものだ。ポピュラー文化の美学は、この種の反動的な見解に応答する用意をしておく必要がある。この問題については、ノエル・キャロルの A Philosophy of Mass Art 134がきわめて有益な議論を与えてくれるだろう。キャロルは、コリングウッド、グリーンバーグ、アドルノといった論者たちによるポピュラー芸術への非難を類型化したうえで、それらの問題点を指摘している。ドミニク・ロペスの A Philosophy of Computer Art 135もまた、この種の非難に対するひとつの応答を示している。また、The Routledge Companion to Aesthetics 43に所収のジョン・フィッシャーの論文 “High Art versus Low Art”136は、「高級芸術」と「低級芸術」を対比させる議論一般についての概説になっている。
当のポピュラー文化の形式は芸術形式なのか、つまりそれは美学の対象として適格なのかという問題は、ポピュラー文化の美学の入り口にすぎない。その中心的な問題はむしろ、それぞれのポピュラー文化の形式が、一個の芸術形式としてどのような独特の特徴や哲学的な問題をもつのかという点にある。この問題設定はまた、近年の分析美学における「芸術一般の哲学から個別芸術の哲学へ」という流れとも密接に結びついている(「芸術の定義」の解説文を参照)。
ある芸術形式が固有に持つ特徴は、しばしば「媒体固有性(medium specificity)」と呼ばれる。キャロルの The Philosophy of Motion Picture 137は、映画の媒体固有性を論じるだけでなく、映画は芸術か否かという古典的な問題や、媒体固有性を考えることについての一般的な問題を細かく論じている。この点で、この本はポピュラー文化の美学一般の手引きにもなる。
媒体固有性の議論を含めた個別芸術の哲学という観点から実際にどのような問題が見いだされてくるかは、それぞれのポピュラー文化によって異なるだろう。以下、ジャンル別に文献と論点をいくつか紹介しよう。
ポピュラー音楽の美学では、とりわけ存在論的な問題がさかんに論じられている。たとえば セオドア・グレイシック Rhythm and Noise 138 や アンドリュー・カニア “Pieces of Music” 139 や 今井晋「ポピュラー音楽の存在論」140は、ロックやジャズにおける「作品」や「演奏」が独特の存在論的性格をもつものであることを論じている。
The Art of Comics 141は、芸術の哲学の観点からコミックを論じたアンソロジーである。コミックの定義やコミック作品の存在論から、コミックにおける画像と言語の関係にいたるまで、幅広い論点がとりあげられており、現在の分析美学におけるコミックの哲学の範囲と水準を示している。スコット・マクラウドの『マンガ学』142は、それ自体は哲学書ではないものの、そこでなされる問いと答えはきわめて分析美学的であり、実際にコミックの哲学の文献でしばしば引用される。
グラント・タヴィナーの The Art of Videogames 143は、同様の分析美学的な問題設定をビデオゲームに適用している。そこではとりわけ、その「インタラクティブなフィクション」としての性格のおかげで、ビデオゲームがどのような媒体固有性をもち、そしてどのような哲学的・倫理的な問題を引き起こすかという点が綿密に議論される。ビデオゲームを含めたインタラクティブな芸術一般の本性については、ロペスの A Philosophy of Computer Art 135もまたコンパクトで優れた議論をおこなっている。
デジタル映像によるものを含めた映画一般の哲学については、先述のキャロル137に加えて、ベリス・ゴートの A Philosophy of Cinematic Art 144を挙げたい。分析美学的なアプローチからは離れるものの、トーマス・ラマールの『アニメ・マシーン』145もまた、日本のアニメを中心としたアニメーションの媒体固有性に焦点をあわせているという点で、適切な意味でポピュラー文化の美学に含まれるものだろう。
ジェーン・フォーシーの The Aesthetics of Design 146は、デザインの定義や存在論といった問題から議論をはじめる点で、典型的な分析美学的アプローチである。とはいえ、その議論の射程は、たんにデザインをとりまく美的文化にとどまらず、われわれの日常や人生における美的実践の意義にまで及んでいる。(松永伸司)
153
Noël Carroll
Routledge
※邦訳『批評について(仮)』(勁草書房)刊行予定
>>解説文を開く
20世紀以降、芸術的価値をめぐる議論は大いに発展したが、その背景には主に二つの要因がある。一つは、芸術や大衆文化の拡大・多様化である。分析美学という分野では、20世紀、芸術の定義をめぐって議論が大いに進展したが(「芸術の定義」の項を参照)、芸術の価値をめぐる議論においても、その影響はつよく見てとることができる。もう一つの要因は、哲学・倫理学の分野で価値(value)についての考察が進んだことである。価値の内在性・外在性や、価値の看取の仕方などについて、概念や事柄の分析は大いに進んだ。
こうした流れを受けて、芸術的価値をめぐる議論は、現在、問いの形も答え方も格段に進歩している。芸術は何か他の利益をもたらしてくれるから価値があるのだろうか、それともそれ自体で価値をもつのだろうか? 芸術の価値とは、単一の価値なのだろうか、それとも美的価値や認識的価値といったいくつかの価値から成る複合的な価値なのだろうか? ある芸術作品の価値は他のもので代替可能だろうか? 作品の売買価格と芸術的価値とは無関係といえるだろうか?* こうした問いをめぐる現代の論争において、もはや昔ながらの素朴な芸術観に依拠して芸術的価値を論じることはできない。残念ながら、このトピックについて日本語で読める文献は非常に限られている。近年の主な議論についてはステッカー『分析美学入門』34 第11章「芸術的価値」を見てほしい。
キーラン Revealing Art 147 は、芸術的価値をめぐる現代の様々な議論をわかりやすく紹介してくれる好著だ。古典作品から現代アートまで、具体的な作品を細やかに分析・解釈しつつ論述を進めていくその手つきは、美学という学問の魅力を十分に伝えてくれる。道徳的価値について論じる箇所にはわたしには賛同しかねるところも多少あるが、その点を差し引いても、この分野ではまずはオススメの一冊だ。
芸術的価値をめぐる議論のなかで、近年とりわけホットだったのは、道徳的価値との関係についての議論だ。エルゲラ『ソーシャリー・エンゲージド・アート入門』148 が示しているように、近年では、社会と積極的に関わろうとする芸術が現代アートの一ジャンルを占めるまでになってきた。また、表現規制や展示規制をめぐっては毎年スキャンダラスな事件が多数起こっている。芸術と道徳との関係をめぐる問いは、古めかしいどころか、社会制度設計においてもアート業界においても、まさにアクチュアルな問いなのだ。
分析美学の分野でも、そのことは例外ではない。芸術的価値と道徳的価値との関係については、ここ20年ほどの間に議論が大きく進展した。この領域には、両価値をまったく無関係なものとみなす自律主義(autonomism)、道徳的良さは芸術的価値を高めうるとする倫理主義(ethicism)、悪や暴力といった要素が芸術的価値を高めうるとする不道徳主義(immoralism)などの立場があり、いまも論争が続いている。ジェイコブソン「不道徳な芸術礼賛」31 は、近年の哲学的議論のなかで不道徳主義を擁護する先鞭をつけた論文であり、この論争をフォローするには必読の文献だ。また先に挙げたキーランも不道徳主義擁護の立場をとっている。一方、ゴート Art, Emotion, Ethics 149 は倫理主義の立場を強く押し出している。不道徳主義や自律主義に反論しつつ自説を精緻に擁護していくゴートの論述の進め方は、芸術哲学特有の知的興奮を十分に味わわせてくれるだろう。残念ながらこのトピックに関しても日本語で読める文献は少ないのだが、数少ない例として『分析美学入門』34 12章「価値と価値との相互作用:倫理的価値、美的価値、芸術的価値」、西村清和『プラスチックの木で何が悪いのか』53 第5章、拙稿「作品の倫理性が芸術的価値にもたらす影響――不完全な倫理主義を目指して」150 を紹介しておく。
不道徳作品を考える上でとりわけ避けては通れないのが、ポルノグラフィーである。ポルノの価値はどこにあるのか? ポルノと芸術とは原理的に区別できるものなのか? ポルノははたして不道徳なのか、不道徳だとしたらどこが不道徳なのか? こうしたポルノをめぐる議論の幅広さと奥深さを伝えてくれるのが、論文集 Art and Pornography 151 である(編者の一人であるレヴィンソンは『分析美学基礎論文集』収録の「文学における意図と解釈」97 の執筆者でもある)。とはいえここでは、ポルノをめぐる表現規制の仕組みやそのベースにある考え方は国によって様々であり、英語圏の議論をすぐさま日本の状況に適用できるわけではない、ということも付言しておこう。加藤隆之『性表現規制の限界――「わいせつ」概念とその規制根拠』152 は分析美学の書物ではないが、表現規制問題を考えるにあたって避けては通れない法学的議論をアメリカと日本の判例を用いて丁寧に論じてくれている好著だ。
芸術的価値に関する話題として、最後に、近年再び「メタ批評」の議論が盛り上がりを見せていることを紹介しておこう。分析美学という学問分野が批評文の言語分析からスタートしたことに鑑みれば、これはある意味で原点回帰ともいえる興味ぶかい動向だ。キャロル On Criticism 153 は、芸術批評という営みを改めて哲学的に考察しつつ、〈批評とは理由に基づいた価値づけ(reasonable evaluation)だ〉という姿勢を押し出している。似たような話題を扱った書物として、作品記述についての古典的な入門書であるバーネット『美術を書く』154 があるが、これとキャロルの議論とを比較すると、批評という営みがいかなる思想に基づいているのかについて、さらなる理解が得られるだろう。(森 功次)
* 文化経済学、芸術社会学の書物ではあるが、芸術的価値と金銭的価値との関係を考えるための好著として、アビング『金と芸術――なぜアーティストは貧乏なのか』155、フィンドレー『アートの価値 マネー、パワー、ビューティー』156 を挙げておく。
158
Elisabeth Schellekens & Peter Goldie (eds.)
Oxford University Press
>>解説文を開く
芸術鑑賞をはじめとして、美的経験にはさまざまな心的活動が関わっている。すぐ思いつくだけでも、作品の知覚、それによって喚起される情動や想像、作品に関する知識や概念の行使、作品についての思考や評価的判断の形成、といったものが挙げられるだろう。こうした心的活動はそれぞれ哲学や心理学で昔から探求されているし、近年では、心についての神経科学的アプローチの発展が目覚ましい。また、生物学や人類学、比較文化研究からも、心とはどういったものであるかを知ることができる。心に関するさまざまな研究領域の総称は「認知科学」と呼ばれるが、最初に述べたように美的経験にさまざまな心的活動が関わるなら、美的経験とは何かを解き明かすうえで認知科学の知見が重要な示唆を与えてくれるに違いない。それどころか、いずれは認知科学を無視して美的経験について語ることはできなくなるかもしれない。少なくとも、現在の心の哲学が科学的知識なしにはほとんど行えない状況にあるのをみると、美学にもそうした動向がいずれやってくると予想される。実際に、近年の美的経験に関する議論では、科学的知見に基づいたものが増えつつある。
美学と認知科学の橋渡しとなるものとしてまず挙げられるのは、他のセクションでもたびたび言及されているシブリーの著作集 Approach to Aesthetics 157 だろう。本書には、美的判断や美的性質に関わる知覚的側面について、非常に示唆的な見解がいくつも見出せる。こうした見解は、知覚を介して美学と認知科学を結びつける鍵となるものであり、本書のなかでもとくに、『分析美学基本論文集』にも収録されている「美的概念」23は、美的知覚に関する現代の議論では必ずといっていいほど言及される。
次に、「現代美学と認知科学」というセクションタイトルにうってつけの論文集として、 Aesthetic Mind 158 を挙げておこう。この論文集では、美学と心理学の関係、美的経験における情動、美と普遍性、想像とメイクビリーブ、フィクションと感情移入、音楽やダンスと表現性、描写と鑑賞、といったさまざまなトピックについて、美学者、哲学者、心理学者、神経科学者、人類学者、霊長類学者といったバラエティー豊かな研究者が議論を提示している。これらのトピックは他のセクションでも取り上げられているが、本書ではそこに認知科学がどう関わるかを知ることができるだろう。(執筆者の専門とトピックの幅はもう少し狭いが、同様の趣旨の論文集としては Aesthetics and the Sciences of Mind 159 や Aesthetic Science: Connecting Minds, Brains, and Experience 160 も挙げられる。)
美学と心理学・神経科学を接続させる試みは「実験美学」や「神経美学」と呼ばれることがあるが、それに関する日本語の文献で最も手に取りやすいのは、川畑『脳は美をどう感じるか』161 だろう。この本では、絵画に向けられる視線、美的な能力の進化、アウトサイダーアート、黄金比など、実にさまざまなトピックが取り上げられ、それらに対する科学的アプローチが展開されている。本書を読めば実験美学や神経美学のおおまかな見取り図を知ることができるだろう。(とりわけ進化と絵画の関係に興味を持つ人には、同じく手に取りやすい本として、齋藤『ヒトはなぜ絵を描くのか』162 を勧める。)
さらに踏み込みたい人には、『美から脳を考える』163 を勧める。知覚に関する研究では視覚についての考察が大半を占めており、そのため芸術作品に科学的にアプローチする際には絵画の事例が非常に多いのだが、この論文集では、音楽やダンス、詩、そしてそれらの文化的な差異など、他ではあまりみられない興味深い事例が多く取り上げられている(もちろん、美的経験に関わる視覚情報処理に関する論文も収録されている)。また、ザイデル『芸術的才能と脳の不思議』164 では、脳の損傷が美的・芸術的活動にもたらす影響に関する多くの事例が紹介されている。特定の脳領域に損傷を負った人は絵画や音楽の鑑賞が不可能になったり絵を描くことが困難になったりするが、こうした事例は、その脳領域が美的経験・創作能力にどのように寄与しているかを明らかにする手掛かりとなるのである。
ここまで挙げてきた文献では視覚についての科学的知識が前提とされていることが多いが、それを詳しく知りたい人は、下條『視覚の冒険』165 を読むといいだろう。この本では、錯視をはじめさまざまな視覚現象を手掛かりとして、視覚に関するさまざまな科学理論が概説されている。(視覚認知にさらに踏み込みたい場合は、認知科学の最重要書のひとつであるマー『ビジョン』166 を読むのがいいだろう。)(源河 亨)
172
デイヴィッド・ウィギンズ
(大庭健・奥田太郎 編・監訳)
勁草書房
>>解説文を開く
「美的(aesthetic)」という形容詞は、経験(experience)、価値(value)、概念(concept)、判断(judgment)、態度(attitude)、対象(object)、形式(form )など、さまざまな名詞の上に付して用いられる。分析美学の領域では、これら美的経験、美的性質、美的判断などをまとめて、「美的なもの(the aesthetic)」と呼ぶ。この「美的なもの」をどのように理解すべきか。これは分析美学にとどまらず、美学の長い歴史の中で絶えず問われ続けてきた一大問題だ。
初期の分析美学は、「美的」という言葉の使い方を分析するという言語分析をひとつの重要な作業としていた(3-D「美学と言語」の項を参照。『分析美学基本論文集』所収のシブリー「美的概念」23 や、同著者の論文集 Approach to Aesthetics: Collected Papers on Philosophical Aesthetics 157 所収の論文 “Aesthetic and Nonaesthetic” はその嚆矢である)。だが「美的なもの」をめぐる近年の議論は、知覚の哲学や価値論、メタ倫理、性質の形而上学など発展をうけつつ、より多様な方面から考察が進んでいる。そこでのひとつのトピックは、経験、性質、形式などの中でどれが美的なものの根幹にあるのか、という問題である。その根幹が定まれば、他の〈美的なもの〉はその根幹を軸に説明することができる。たとえば〈美的なもの〉を美的経験を軸に理解しようとする立場からすれば、美的性質は〈美的経験を喚起する性質〉、そして美的形式は〈それを知覚することで美的経験が引き起こされる形式〉といったかたちで規定される。一方、美的性質を軸にする立場からすれば、美的経験は〈美的性質の知覚をつうじて引き起こされる経験〉などと規定されるわけだ。古くはビアズリーが Aesthetics 167 において美的形式の存在を主張していたが、ダントーは The Transfiguration of Commonplace 29 でウォーホルの《ブリロボックス》を事例にしつつ、知覚的には判別不可能なものに異なる美的価値が付与されうると主張し、これに反論した。つまり、美的形式のみでは、なぜそれが芸術になるのかも、なぜそれが価値をもつのかも説明できない、というわけだ。また、見た目が同じものでも対象をどのカテゴリーにおいて知覚するかによって見方が大きく異なる、という点についてはウォルトン「芸術のカテゴリー」25 が説得的な議論を展開している。
美的性質は実在するのか、という問題は長くつづく伝統的な問題でもあるが、近年ではゴールドマン Aesthetic Value 168 は美的性質の反実在論を、ザングウィル The Metaphysic Beauty 169 は美的性質の実在論、形式主義を、それぞれ擁護している。またレヴィンソンの論文集 Contemplating Art 170 の第5部にも美的性質についての議論がある(このあたりの議論は『分析美学入門』34 第3章、第4章でおおまかな見取り図をつかむことができる)。
何を軸に美的なものを理解するにせよ、また美的性質の存在論的地位をどのように定めるにせよ、各論者に概ね共通しているのは、美的経験はある種の感性的経験であり、それは主観に根ざした経験である、という考え方である。つまり、美的なものは何らかの観賞経験と切り離し難く結びついており、その経験と完全に切り離して論理的・客観的視点のみから説明することはできない、というわけだ。この考え方は18世紀に美学が成立して以来、現代まで多くの論者が受け入れている。問題は、その美的性質や美的判断が根ざしているとされる経験を、どのような経験として、また誰の経験として理解すればよいのか、である。
この問題を考えるにあたって、理想的批評家(ideal critic)を想定するというのはヒューム以来伝統のある切り口だ 4 。この理想的批評家をめぐっては、論法を洗練させつつ現代も議論が続いている。ヒュームのいう理想的批評家はわれわれ現実の観賞者にとってどのような位置づけを持つのか、という問題を提起したレヴィンソンの論文 “Hume's Standard of Taste: The Real Problem” は上述の論文集 170 に収録されている。また、この辺りの議論については、ロスの論文 “Ideal Observer Theories in Aesthetics” 171 が20世紀半ばから最近までの議論を簡潔にまとめてくれているので、まずはこれを読むとよいだろう。日本語の文献では、やや難解だがウィギンズ『ニーズ・価値・真理』172 所収の論文「賢明な主観主義?」がヒュームの理想的観賞者に関する議論に触れている。また近刊のマクダウェル倫理学論文集 173 には第二性質(二次性質)について考察した論文「価値と第二性質(Values and Secondary Qualities)」が収録されており、その結論部では素描的ながら、趣味や美的確信をめぐる問題との接続も図られている(近年の美的性質・判断をめぐる議論は、倫理学における道徳的性質・判断をめぐる議論と相互に影響関係にあり、議論を追うためには双方の論争状況に目をくばる必要がある)。
紹介しておきたい一つの動向としては、近年、〈芸術作品については実際に作品を直接観賞しなければ正当に判断できない〉という考え方をめぐって活発な議論が行われている、という点である。「直面原理(Acquaintance Principle)」と呼ばれるこの考え方を提出したのはいまでは古典ともいえるウォルハイムの Art and Its Objects 69 だが、その原理の是非をめぐって近年ふたたび議論が盛り上がっているのだ(その背景には認識論や知覚の哲学の隆盛があるとみてよい)。なるほどこの原理は一見すると常識のようにも思えるのだが、この原理はほんとうに正しいのだろうか? 芸術作品についての他人の証言(testimony)は、作品を判断するにあたってどのような役割を持つのだろうか、もしくは何の役割も持たないのだろうか? 知覚不可能な芸術作品についてわれわれはどう判断すべきなのだろうか? こうした問題をめぐる論争は基本的に学術論文単位で進んでいるが、3-B「芸術の定義」の箇所で挙げられたロペス Beyond Art 68 には直面原理をめぐる議論が一部含まれている(「芸術の定義」の項で説明されたように、ロペスはこの著作で、個別の芸術形式について考察することの意義を訴えているが、ロペスは近年、美的価値についても、現状に即したよりよい説明をするためには、ヒュームの想定するような理想的批評家ではなく、個別領域に特化した価値判断の専門家(ロペスはこれを、より狭い領域を照らす専門家という意味で「低ワットの専門家(low-watt expert)」と呼ぶ)について考察すべきだ、という主張を行っている(“Aesthetic Experts, Guides to Value” 174 ))。
また、まだあまり論考の数は多くないが、美的観賞にはどのような徳(態度、能力、姿勢)が求められるのか、といういわば「徳美学(virtue aesthetics)」とでも呼べるような議論が登場しつつある。面白いオススメの論文として、キーラン “The Vice of Snobbery: Aesthetic Knowledge, Justification and Virtue in Art Appreciation” 175 を挙げておこう。キーランはこの論文で、自身の経験に根拠をおかずに周りの社会的状況などを元に美的判断をするという(いわゆる「スノッブ」な)態度を取りあげ、そこに含まれる悪徳や認識論的な問題について議論している。この徳美学という領域が登場してきた背景にも、徳倫理学という近隣分野の隆盛があるとみてよい。近年の徳倫理学の動向については『ケンブリッジ・コンパニオン 徳倫理学』176 や『徳倫理学基本論文集』177 で学ぶことができるだろう。(森 功次)